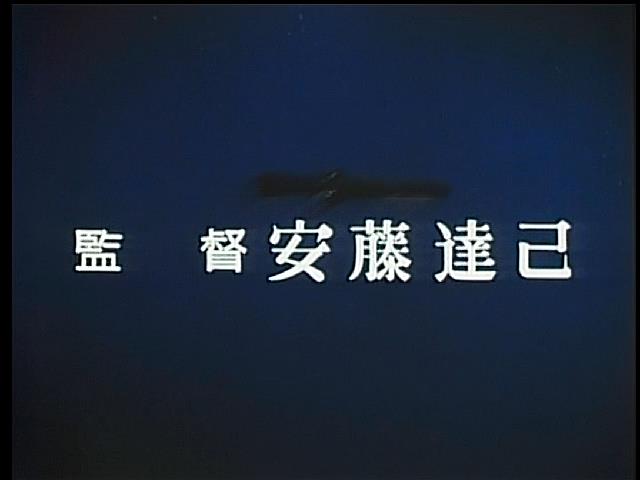前作『ウルトラマン』(1966年)と差別化をした『ウルトラセブン』(1967年)では、そこに登場するのはもちろん、自然現象たる怪獣ではなく、大宇宙から侵略をしてくる宇宙人である。
宇宙人は怪獣と違い、人間に似た姿を持ち、知能を持ち、そして彼らの生まれ育った星には、文明があるという前提で描かれるパターンが多い。
つまり、怪獣が大自然の驚異や天災を戯画化したもう一つの姿だとすれば、宇宙人というのは、異民族のカリカチュアであるという過程が成り立つ。
そもそもからして、日本にとって異民族であった、沖縄人の金城哲夫・上原正三両氏にとって、異民族国家である日本で、その異民族たちに混じり異民族のためのテレビを作っていく上で、さらにその中で、自分らにとっての異民族(日本人)から見た異民族(宇宙人)を、描いていくという、まるで言葉遊びのような多層構造は、はたして、金城氏と上原氏の中でどういう感情を生んでいったのか。
それを現代に生きる我々が簡単に窺い知ることはできないのだが、ある程度までの推察をすることは不可能ではない。
特に上原氏は、円谷プロ退社後も東映などの会社で子ども番組に残り続け、自ら「僕には、宇宙人やロボット、サイボーグの出てこないドラマは書けない」と明言して仕事を続けてきたわけではあるが、そういったコメントを意識した上で、氏の膨大な作品群を見渡すときに、ひょっとしたら作者たる上原氏自身も自覚していないかもしれない、上原氏ならではの共通点というものが見つかることもあるのだ。
そのキィワードは「異邦人は、我々と同じ姿をしたまま、いつの間にか身近にいる」である。
思えば、氏のウルトラデビュー作品である『ウルトラQ』(1966年)の『宇宙指令M774』からして、そういう物語であった。
地球を守る宇宙指令を帯びて地球にやってきたルパーツ星人は、どこにでもいる女性の姿をして、遊覧船の船上で現れた。
古今東西子ども番組で「人間の姿をした宇宙人」というものは、テレビ作劇のドラマツルギーからいえば、どこかに異質な雰囲気を持たせるのが、常套手段でありセオリーであった。
それは、ウルトラシリーズでも健在であり、例えばそれは『ウルトラQ』『ガラモンの逆襲』のセミ人間の人間体が持つ中性的な怪しさであったりもしたであろうし、それはバルタン星人にのっとられたアラシの描写や、ゼットン星人に姿を借りられた岩本博士の挙動にも現れている。
しかし、上原氏の描く「人間の姿を借りた宇宙人」はどこか違う。
本話に登場するおもちゃじいさんであっても、それは(満田演出プランニングでもあろうが)その裏にある邪悪な侵略者の顔を見せるときは、はっきりと宇宙人的・悪役的な演技を見せるのではあるが、普段、屋台で玩具を子どもに売りさばいているときの描写は、どこからどう見ても、子ども好きな老人にしか見えない。
いや、演出の方向性の問題ではないのかもしれない。
上原氏は他の『ウルトラセブン』での作劇キャラ配置でも、ラリーの参加者(『700キロを突っ走れ!!』)や、事故死者(『侵略する死者たち』)、モンキーセンター所員(『恐怖の超猿人』)、団地の住人(『あなたはだあれ?』)などなど、存在そのものが日常風景に溶け込んでいる者達が、実は裏を返せば宇宙人(自分達とは違う異民族)であるという仮想現実を描いてきた。
それは、その時々の監督や演出プランによっては、いかにも怪しく描写されることもあったわけだが、そこで常に変わらないのは、その異質で異邦人な存在達は、ありがちな場所でありがちな姿を装って、我々の社会の風景の中に潜んでいたという事実。
それは『帰ってきたウルトラマン』(1971年)以降でもスタンスは変わらず、新マンシリーズ屈指のイベント編でもあり事実上の最終回といわれた『ウルトラマン夕陽に死す』『ウルトラの星光る時』前後編に登場する、残虐で悪辣なウルトラマン抹殺を企むナックル星人の描写に当たっても、人間の姿を借りているときの宇宙電波研究所長としての描写で、見学に来た子どもたちに対して優しい笑顔を見せるシーンを、上原氏はわざわざ挿入している。
このエピソードでは、坂田兄妹の死、ウルトラマン抹殺計画、MATの危機、そして初代ウルトラマンとウルトラセブンの競演といった、詰め込まなければいけないガジェットが満載であるにもかかわらず、あえてそこに、ナックル星人の人間体が、日常社会に溶け込んでいる描写を挟み込んでいるのだ。
(逆に、『ウルトラセブン』で他作家によって書かれた『怪しい隣人』(脚本・若槻文三)では、まさに「宇宙人が隣の家に存在している」というメインテーマを扱いながらも、そこで登場する宇宙人男性の描写に「日常」は全くなかった)