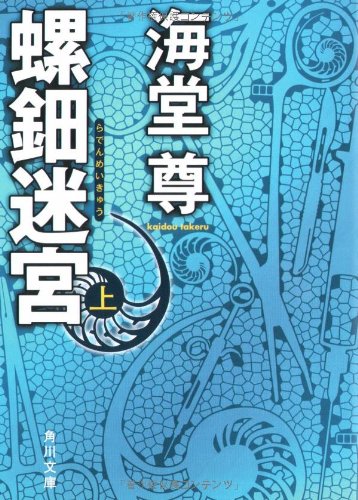もっとも、そこ(医療専門用語の操り方)が上手いという要素だけならば、現実の大病院の現役勤務医であるという海堂氏のキャリアを前提にすればそこには何も不思議はない。
タクシーの運転手の人に、タクシードライバー同士の会話を書かせれば、多少文才がなくても、きっとその文章にはリアリティが自然に湧き出るだろうし、それはどの職業に対しても同じことが言えるだろう。
医療に関わらず、今の時代は様々な職業や業種・業界の内幕ドラマや小説が流行り、昔のような「フィクションの為の嘘」は必要とされなくなったのだ。
料理、金融、政治、司法、軍事、スポーツ等の専門ジャンルを舞台とした作品に対し、大衆は柔軟に、いかにもなリアリズムを求めるようになり、そのニーズに応えるために、小説や漫画、ドラマは常に、作劇者とは別個に、題材で扱う分野のプロを、アドバイザーや原作者として、招聘することが当たり前になってきている。
そうなると、そこで招かれた「その道のプロ」と、招いた側の「作劇のプロ」とのパワーバランスにおいて、どちらがどこまで踏み込むのか、どちらがどこまで主導権を握れるのかが、読者のニーズを満たせるか否かの、鍵になってくるわけだが、その二者が二人三脚で作劇に挑むのではなく、最初から一人が両者を兼ね備えたら、という理想をかなえたのが、海堂氏の小説群なのだと仮定することも可能だ。
その場合、現役の大病院勤務医(当時)が、大病院内での群像描写を行うのだから、そこでのやり取りがリアリズムに溢れているのは、これはある意味で当たり前に思われるだろう。
実際、ここまでも書いてきたように、シリーズを通じて、手術中の会話はもとより、勤務中の看護師の会話や、ちょとした医療スタッフ同士のやり取りに至るまで、海堂氏のダイアローグコントロールは見事なまでの巧みさで、リアリズムといった言葉を越えた「生々しさ」までをも、読んでいる一般人に伝える力を持ち合わせている。
ポイントは、そこからさらに(海堂氏のダイアローグコントロールは)一歩踏み込んで、それが「専門知識がない人が、解説がないまま読んでも、なんとなく、そこで交わされてる会話の内容を理解してしまえる」というところだろう。
それゆえに、逆にだからこそ「非医療系登場人物の会話の陳腐さ」や「(マンモス病院という舞台故の)膨大な登場人物数バリエーションさにはほど遠い、登場人物の描き分けバリエーションの少なさ」などは、これはさすがに、海堂氏が非文系であるがゆえの、仕方ないウィークポイントになっているのだ。
誤解を恐れない言い切りをしてしまえば、もしも海堂氏が、医療現場を舞台にせずに、例えば「20代青年と女性の恋愛を題材にした青春小説」や「単なる殺人事件を材にしたミステリー」などを書いたとしたら、おそらく、幼稚で陳腐な三文小説に仕上がってしまうのではないかという危惧は、デビュー作『チーム・バチスタの栄光』とは意図的に趣向を違えて構成されたシリーズ第二段の『ナイチンゲールの沈黙』が、半ば証明してしまっている。
しかし逆を言うならば、非文系の海堂氏の、そこの弱点をまったく感じさせないほどに、本作『チーム・バチスタの栄光』は、徹底した「大病院・医療の世界」という、閉じた世界で物語が進んでいて、これは『パラサイト・イヴ』の瀬名氏にも共通して言えることなのだが、理系の道を選び、勤しみ、人生をひた進んできたはずの学者や医者が、いきなり文学創作の世界へ手を伸ばすということはつまり、その人は、並大抵の文学青年以上にロマンチストである可能性がまず高い。
そのことは、海堂氏の場合は本書よりも『ナイチンゲールの沈黙』に顕著である。
その詳細は、また改めて『ナイチンゲールの沈黙』論で述べたいと思うが、『チーム・バチスタの栄光』の場合は、そこで登場するほとんど全てのキャラが、作者・海堂氏が日常で接しあう属性の、医療現場の関係者やスタッフであるので、そこでは彼らは「あえて洞察し創作する必要のない自然なリアリティ」に溢れているが、ここで舞台や登場人物の属性が、海堂氏のメインフィールドである、病院や医療関係者から、一歩でも離れてしまうと、途端に描写の底が浅なり、メンタリティや掘り下げ深度が陳腐化し、台詞や会話は、安っぽく臭くなってしまうのだ。
いくつか例を挙げるなら、『ナイチンゲールの沈黙』での、伝説の歌姫歌手とマネージャーのやり取りや、『螺鈿迷宮』においての、女性記者と同窓生の主人公の会話など、病院内部の、硬質でシビアなリアリズムに溢れた空気感とは、ほど遠くギャップが大きすぎる「安いドラマ」が、そこでは展開してしまう。
幸い(というべきか)処女作『チーム・バチスタの栄光』では、物語は最初から最後まで、主舞台の大学病院を一歩も出ることなく進行し、登場人物も一人残らず(患者も含めて)医療関係者なので(本シリーズの主役コンビの片割れである白鳥圭介に関しても、厚労省官僚だからして、医療関係者の枠内ではある)その辺のボロは出なかったものだと思われる(余談だが、そういう特色を無理矢理ミステリー世界の不文律に当てはめて考えると、この作品は、ミステリージャンルでいうところの「クロードサークル」の変種であるのかもしれない)。
しかしそこは、さすがに海堂氏は、文学創作者としては初心者で、試行錯誤をするしかなかったのだろう。
次作『ナイチンゲールの沈黙』では、前作とは趣向を変えようと腐心して、登場人物や展開に変化を求めすぎてしまった結果、医療関係者と、それ以外の人物とにおけるリアリズムのギャップが、完成した原稿の上で、アンバランスに浮き出てすぎてしまい、クライマックスにキーとなる設定も、ちょっと現実離れし過ぎた、SF的な、オカルトチックな超常現象を、事件解決の鍵に持ち込んでしまった。
それもこれも、海堂氏ならではの「非情で冷酷な、医療や社会の現実」と「医学者だからこそ夢見てしまう、その先にあるロマンティシズム」の融合を目指したかったことは、痛いほど理解できるのではあるが、悲しいかな、さすがに天はそこまで二物を与えることはなく、その二つは、水と油のように違和感しか残さなかった。
その反省からだろうか。海堂氏は、続く『ジェネラル・ルージュの凱旋』以降の諸作品においては、独自がもつロマンティシズムを、医療の内側で奮闘する人々の葛藤へと落とし込み、そこでの「医療人としての生き様」と融合することに限定して、一定の成功を収めている。
次回「なぜ『チーム・バチスタの栄光』は推理小説だったのか・後」