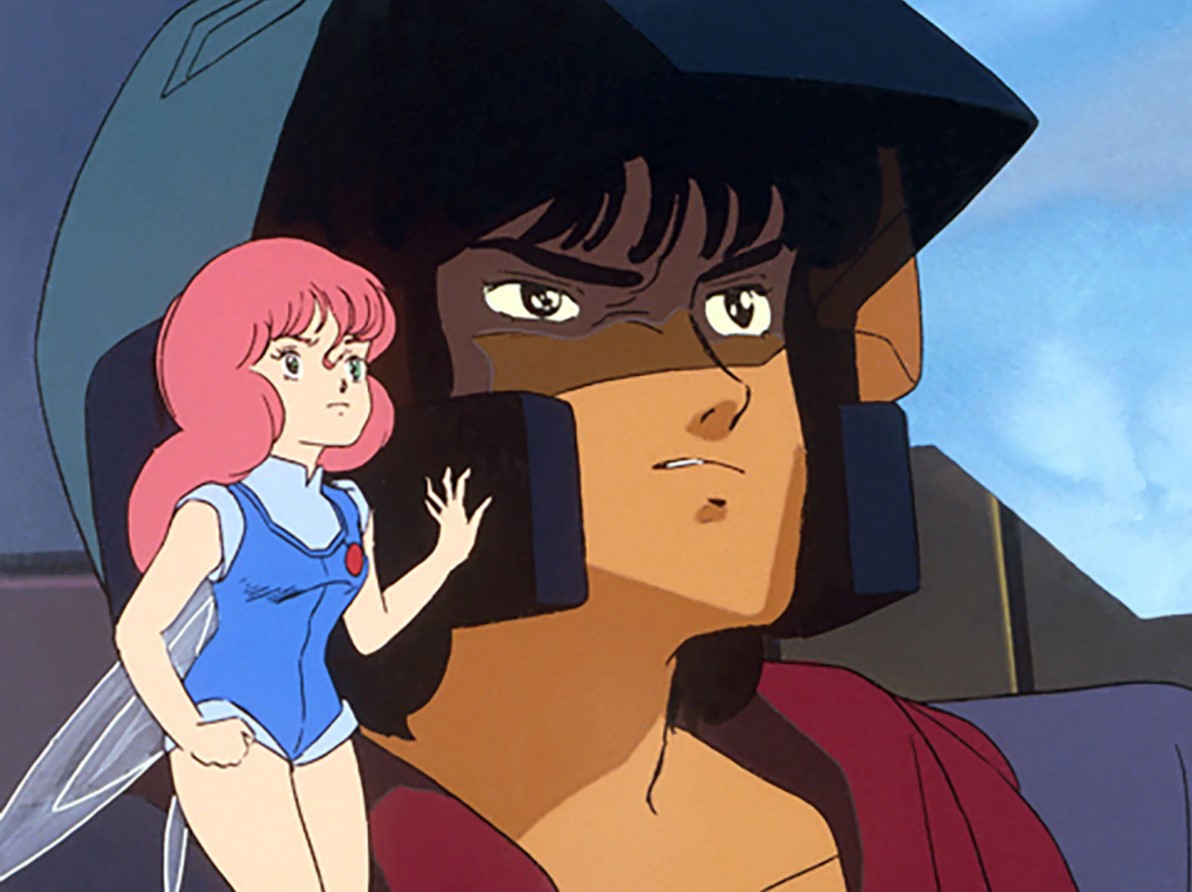「異次元」という概念は、ウルトラシリーズで何度も描かれる素材である。
その元祖は、『ウルトラQ』(1966年)における、『2020年の挑戦』や『あけてくれ!』などの作品であり、むしろ『ウルトラQ』はその全ての作品世界観が、なんらかの形で異次元的な状況や概念との接点を描くシリーズであった。
やがてウルトラにおける異次元は、『ウルトラセブン』(1967年)の『怪しい隣人』などを経て、まさにそのまま「異次元人」の侵略を描いた『ウルトラマンA』(1972年)へと受け継がれるのだが、そこまでの作品を改めて辿っても、セブンの『円盤が来た』や『第四惑星の悪夢』、本作『ウルトラマン』(1966年)の『恐怖の宇宙線』や『恐怖のルート87』など、常にウルトラシリーズは、現実世界とほんのちょっと乖離した、浮遊感のような感覚を描き続けてきて、それはある意味で我々三次元世界の住人が認知することが出来ない、異次元・四次元という概念と、どこかしらでリンクしていたのではあるまいか。
そういった浮遊感覚をウルトラの趣として楽しむ人にとっては、『ウルトラマンA』後半以降のSFイズムの失速感は深い失望となったのであるが、それはしかし、非現実的な異次元という概念と、我々の生きる現実との接点が、70年代以降、様々なオカルティックなタームや要素を経て増えていったからでもあり、例えるならUFOだったり終末的予言の世界だったり、人はいつでも現実に生きながら、でもどこかで、非現実への逃避を心願っている存在なのだとも言える。
そういった異次元という概念の根底にある厭世観への甘美な切望を、メタファーな解析そのままに物語化したのが、前述した『あけてくれ!』だったわけだが、その一方で本話は、その異次元の立脚点を徹底して「シュール」という手法と概念に、置き換えて表現が行われている。
そこで特筆すべきは、もちろん飯島敏宏監督の手腕であろう。
映像作品には、映像力学や映像構築論というものがあって、それは例えそれが子ども向けでもコメディであっても、必要不可欠な要素であるのだが、本話では、飯島監督によるその高い力量を感じることが出来る。
例えば、筆者が山際永三監督とお話をさせて頂いたときに出てきた言葉に「モンタージュ理論」というのがある。
それは映像理論の基本中の基本であって、この言葉を知らない映像作家は、まずいないだろうと断言できるのだが、その理論は単純明快で、わかりやすくはっきりしているからこそ、それを実際の映像のコンティニュティにおいて、どう扱うかの手さばきが、その作品を手がける映像作家の個性であり手腕なのである。
といっても、映像作品を見る一般の視聴者側にとっては、必ずしも常識的な言葉ではないので、モンタージュ理論を、筆者なりの知識で説明させていただこうと思う。
例えば、今貴方の手元に一枚の写真があったとする。
そこには、泣いている少女の顔が映っていたとする。
そのワンショットを見ただけでは、少女の泣いている理由はわからないし、その切り取られた一瞬が、泣き止むところなのか、泣き出したところを写したのかすらもわからない。
しかし例えば、その写真の直前に別の写真を見せられていたとしたらどうだろう。
その直前の写真に写っていたのがお墓だとしたら、きっと貴方はそこで、その少女は、愛する人を失った悲しみに暮れて泣いているのだと解釈するだろう。
けど、写真に写っていたのがもしも、照れながら花束を差し出す少年の、はにかんだ笑顔の写真だったとしたら、きっと貴方はそこで、少女は愛された実感に感極まって、泣いてしまったのだろうと解釈するだろう。
お墓と泣き顔の写真の次に、優しそうな老婆が微笑んでいる写真を見れば、少女の悲しみはきっとこの老婆によって癒されただろうと推測するし、逆にどんより曇った空の写真が続けば、少女はこれからも悲しみの中を歩いていくだろうと想像するだろう。
かようにモンタージュ理論というのは、一枚の写真・一つのカットだけで全てを語るのではなく、それをひとつの流れのひとコマであるという仮定にのっとったうえで、前後の写真・カットが存在することで、改めてその「一枚の写真・一つのカット」に、付加価値をつけていくという行為の連続を意味しているのである。