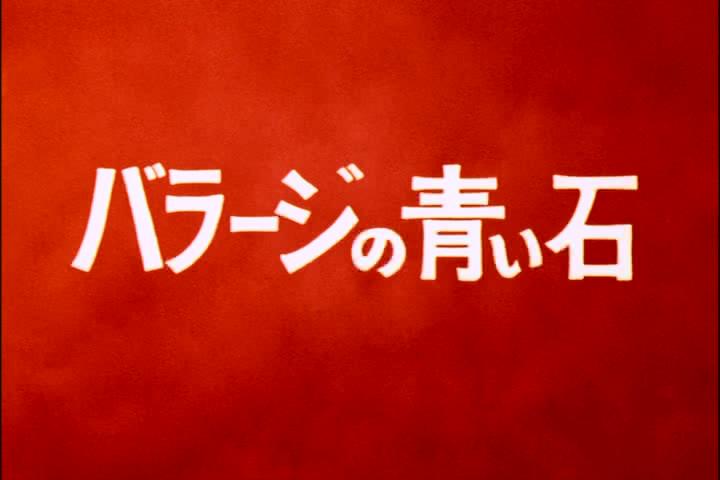『ウルトラマン』では、その制作第一話『侵略者を撃て』において、国家を背負う人間社会が、他国家と戦争に陥ってしまう経過を、SFヒーロー物のカテゴリを使いながら真実をもって描き出したということを、筆者は既に『侵略者を撃て』の評論で述べたわけだが、本話はまた、違ったアングルから「人間が、違う環境の他者と繋がりあうに当たって、何を手がかりにして、向かい合わなければいけないか」を、真理とリアリズムで描き出した作品であろう。
本話における地球人類は「兄弟」という単語・記号と、ザラブ星人の巧妙な戦略で手玉に取られ、いとも簡単に騙されてしまった。
しかしそれは、人類が外宇宙へと向かい、そこで出会うだろう様々な、文化風習・価値観を持つ外界人達と、しっかり繋がっていくために必要な、通過儀礼のような「騙され」ではなかったのではないだろうか?
確かに、馬鹿の一つ覚えのように、騙され続けることは、意味がないし進歩もない。
しかし「何が何でも騙されないぞ」と、最初から偏見を持って相手を伺い、相手の一挙手一投足を全て穿つ見方で受け取る姿勢もまた、危機管理を通り越して、滑稽で見苦しい。
大事なのは、そこで積み重ねた経験を、正しく「次」へと反映させていく、判断力と決断力ではないだろうか。
本話が制作された60年代後半は、アポロ計画も華やかしり頃でもあり、宇宙への憧れは、現実社会への疲れを癒す意味もあって、絶対的にそこには、夢が広がっていた。
ザラブ星人は、それを利用して、地球人の持つ宇宙世界への夢を打ち砕き、そしたまた、ウルトラマンという英雄への信頼感をも打ち砕いた。
そのザラブ星人を、怒りをもって打ち破ったウルトラマンを描いたのは、「ヒーローは完全無欠であれ」が信条の野長瀬三摩地監督だったが、信頼を、夢を、信じる心が、利用されて踏みにじられた展開で、ウルトラマンが颯爽と登場して宇宙人を倒すだけで、そこに爽快感と共に、失われた信頼や夢が取り戻されるという構造は、逆にドラマが硬直化した第二期以降では、描くのが困難になりすぎるか、上滑りしてしまうかのどちらかが多くなるが、しかしこの時期ではまだ、ウルトラマンの毅然とした勇姿こそが、失われたそれらを回復させることができるのだというロジックは、まさに野長瀬監督の真骨頂ともいえるのではないだろうか。
一方で、ではこのドラマのシナリオを組み立てた、金城哲夫氏に関してはといえば、やはりこのドラマ構図に関しては、筆者からしてみると、かつての琉球王朝と、そこへ言葉巧みに政治介入した挙句に侵略し、結果国土を奪い取った大和朝廷という図式を、そこに見出せてしまうのだ。
それは決して、琉球に限ったことではなく、今現代でも遺恨を残している、韓国併合や満州問題に至るまで、アジア諸国の中で抱かれている、日本という国家に対するイメージは、本話のザラブ星人に近いものがあるのもまた事実である。
近隣諸国を、自国より幼い稚拙な存在であると言い切り、貴国のためだというような詭弁を弄して、言葉巧みにその国に取り入り、結果その国と国土を隷属させようとした経過は、金城氏の無意識の奥底の「日本」に対するイメージにも、やはりどこかで影響を与えていたのではなかろうか?
ザラブ星人のデザイン面での「つり目」も、アジア諸外国がイメージする日本人を、如実にカリカチュア化しているともいえる。
しかし、今までの評論でも書いてきたように、金城氏は、その表層意識上においては、沖縄人としての自覚以上に、日本人であろうとする意思が強く浮き上がっていた。
どう頑張っても、沖縄人が本土人に生まれ変われるはずがあろうこともなく、それゆえに、金城氏の帰属意識と実質的な立ち位置は、やがて乖離してしまうのであるが、まだこの『ウルトラマン』時期は、金城氏は前向きに本土人と同化しようと、奮闘努力していた時期でもあって、それゆえ本話では金城氏は、半ば意図的にザラブ星人を「自星の利益のために地球を侵略しようとした宇宙人」ではなく、「様々な星に混乱と混沌をもたらすエージェント」として描こうとしていた節がある。
しかし、金城氏が意図的にずらしたその概念、それこそが、日本を一歩出た諸外国が、第二次大戦時にその視点から見た、日本という謎の国の、おぼろげな印象をそのままに具象化した図であることは、金城氏をして、気づかせることはなかったのだろう。
信頼と、繋がる絆と宇宙への夢を、揺さぶり打ち砕く作劇が、作品を観終った後に、マイナスな印象として残らないのは、それはもちろん野長瀬イズムによる、英雄絶対主義的な映像構造のおかげであるのだが、一方でそれは、金城氏が当時抱いていた、前向きでポジティブな「日本と沖縄は、絶対に一体化できる」という夢への、全幅の信頼感によって、ドラマが構成されているからだろう。
異なった環境の者同士が、社会同士が、繋がりあって一つの関係を築くときには、陣痛もあるだろう、裏切りや苦しみもあるだろう。
けどそれは、きっと絶対に「必要な通過儀礼」なだけであって、それを超えれば、いやそれを超えなければ、その先の関係を掴めやしない。
けども、そのハードルを越えて掴んだ関係は、きっと掴んだその手に、暖かさを感じさせてくれる。
金城氏はそう確信していたのではないだろうか?
当時の金城氏を知る関係者の誰もが、彼をして社交的な人格だと語った。
しかしその裏では人一倍、繊細で傷つきやすい魂が震えていたのは、筆者が今まで語ってきたとおりである。
だから彼は知っていたのだ。
人と繋がる力、コミュニケーションする能力を得るために、その力を使って、誰かと幸せな関係を築くためには、それまでには無数のハードルと困難を、涙と汗にまみれながら越えなければならないという、人が生きていく中での真理と真実を。
人類全体がその困難に阻まれたとき、それを救ったのはウルトラマンだった。
後の上原正三氏や市川森一氏でも描けなかった、真なる英雄の姿が、そこにはあった。