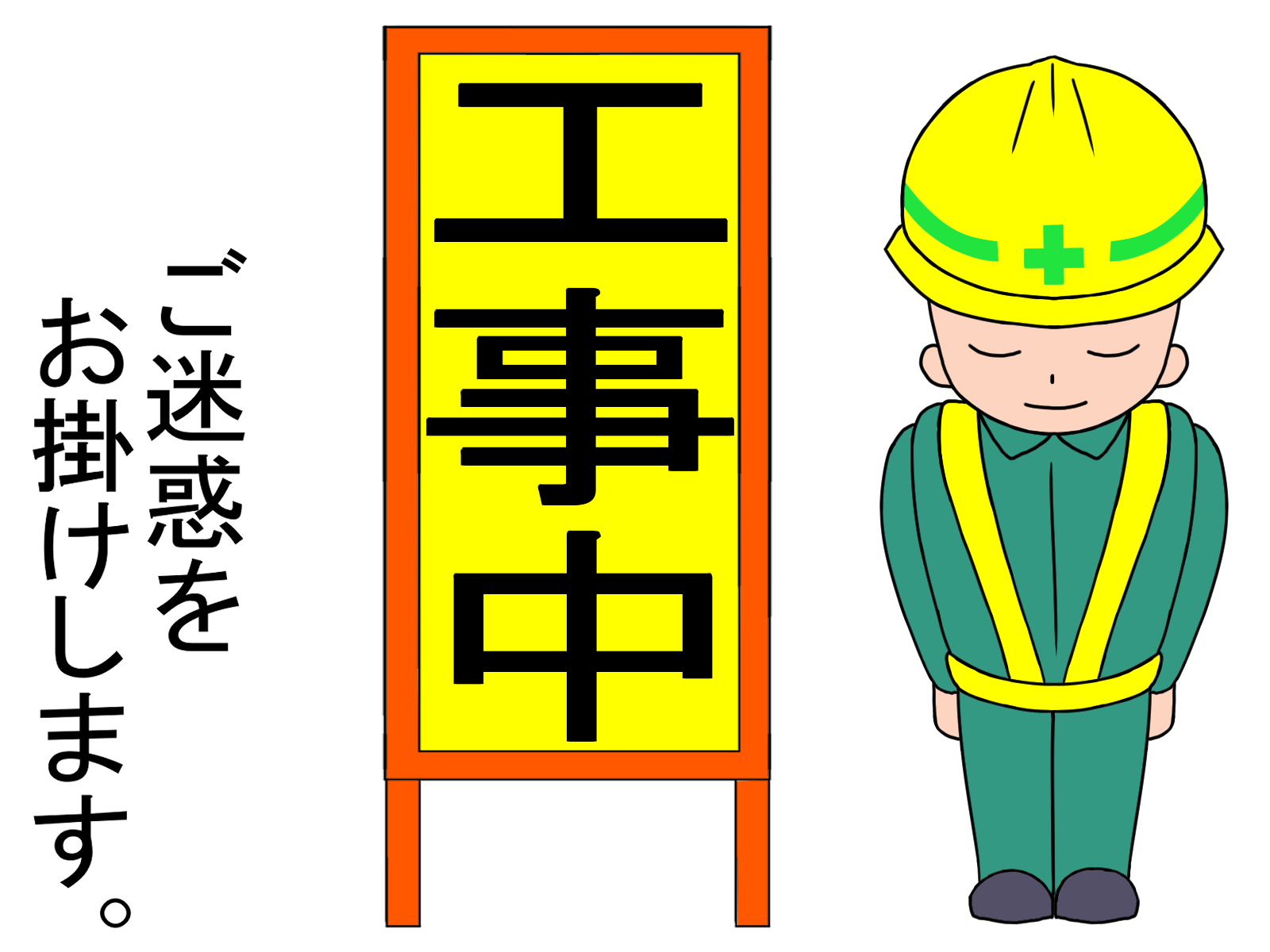『怪奇大作戦』(1968年)
自身のタクト振りに酔いしれる橋本は、さらにショック療法を実行した。
それまで、円谷作品においては、無言のお約束として存在していた「シリーズ第一話は金城・円谷コンビで」を、あえて破壊して、違う作家と監督に任せたのだ。
これを決定した時の橋本は、さぞかし自身の影響力と教育術にご満悦だったのかもしれない。
しかしそれは、「脚本家を鍛え上げる」という教育法としては正しかったかもしれないが、一人のか弱き魂をもった人間を打ち砕くには、充分過ぎる破壊力をもっていた。
「俺がこの国に居続ける目的と理由は、もはや一さんしかない」
最後の「ともだち」に願いと想いを託した金城は、そこに依存した。逃げ込んだ。
もちろん、それは金城の一方的な思い込みであり、それはなんら、円谷一に対して拘束力をもつ要因ではない。
しかしそれは、金城にとっては最後の頼みの綱。
命の綱のようなものであった。
円谷一だけは、自分と同じ想いを抱いてくれている。
自分の想いを共有してくれている。
だから彼さえいれば、自分は自分を否定しなくて良いのだ。
彼が「ともだち」でさえいれば……。
しかし。
『吸血地獄』(金城哲夫脚本 円谷一監督)
この作品の初号試写を観た金城は、全ての終わりを知った。
金城の想い虚しく、円谷一の出した回答もまた「無視」だった。
そこには、金城脚本の変更点を通して「金城の慟哭へ対する回答」が、映像ではっきりと打ち出されていた。
それは、脚本と完成映像を見比べれば、誰もがわかるような形で、「金城の現状への回答=無視」を提示していたのだった。
「一さん、あんたもか……」
初号試写が終了した瞬間、暗く狭い試写室の椅子にもたれて、金城はそう、小さく呟いた。
もう捨てよう。
全てを捨てよう。
もういらない。
「ウルトラの栄光」も「人気作家の栄誉」もいらない。
もう一秒でも、この会社に、この国にいたくない。
がんばった。俺はがんばったんだ。
なんのために? ウルトラのため? 円谷のため? 違う。
自分の未来のため? 地位と名誉のため? 違う!
「ともだち」がほしかっただけ。
自分の、文字にしない思いを、言葉にしない思いを、受け取って抱きしめ、微笑んでくれる「ともだち」を。
それはエゴだと分かっている。
だからがんばったんだよ!
だから必死だったんだよ!
いいじゃないか! それを望んだって!
全員に分かれなんて、俺がいつ言ったんだよ!
たった一人! たった一人! たった一人でいいから!
そんな奴が、ひょっこり俺の前に現れてくれたってよかったじゃないか、それが許されない、そこへの希望もないこの国など、もう居たくない。帰りたい。
そのときを思い出して泣く船上の金城の頬には、太平洋の海風が心地よく当たっていた。
「今まで一緒にがんばってきてくれてありがとう。でも、帰ろう。あの島へ帰ろう、あの国へ帰ろう」
金城がそう言うと、そのか弱い言葉を聞いた妻は優しく頷いた。
『怪奇大作戦』はまだ製作中であったが、金城夫婦は、帰郷へ向けて荷造りをはじめた。
この国と会社と、全ての功績を捨てる決心がついて数日後。
帰郷の準備を進める金城に、田口成光が連絡を取ってきた。
「金城さん、僕の故郷で一緒に過ごしませんか。金城さんは南国出身でしょう? 僕は北国出身なんです。最後に、日本の最後の思い出に、僕の故郷で僕と一緒に過ごしてください」
田口は、金城を兄のように慕い、神のように尊敬し、愛していた。
田口は当時、現場の助監督であり、金城たち文芸や演出には加われなかったが、ずっとずっと、憧れと敬いで金城を見守っていた。
ひょっとすると、金城が捜し求めていた「ともだち」は、ここに居たのかもしれなかった。
数日後。
田口の故郷の信州で、金城は真冬を迎えていた。
別れの時が近づく中、田口は大好きな金城のために、懸命に明るく振舞い、その場を支え続けた。
別れの辛さからくる、千切れるような思いは、きっと田口の方が強かったのかもしれないのに。
豪雪積もる信州の一室で、金城は円谷へ別れの手紙を書いた。
「拝啓。円谷プロの原稿用紙で書く、最期の文章になると思います……。
(中略)
結局こんな風になってしまいました。(筆者注・円谷)一さんとの公私共の生活を考えると
女房と別れるような気持ちです。あるいは男同士の“人間関係”としては、女房以上の物かもしれません。
(中略)
おわび。なぜオヤジ(筆者注・円谷英二氏)と一さんに相談なしにこの雪国に来たか。
私はとてもまともにはこんな自分勝手なことはいえんととび出してきたのです。
一さんは友人(失礼)としても最高です。
心の底から、ああ、この人は本当に友達なんだなあと分かります。
だから、とてもこんないやな話をまともにするなんて出来ないのです。
オヤジもおんなしです。結局こんな風になってしまいました。どうぞ。許してください。
そして出来ることなら私の気持ちもわかってください。
オヤジには手紙も書けません。目の悪いオヤジですもんね。ああ、本当に困った。
許してください。沖縄では事業家になります(後略)」
それが、金城が円谷プロ社員として書き残した「最期の言葉」になった。
そして橋本へ、帰郷を決めた意志を電話で伝えた。
「おい、金ちゃん! 待てよ。もう一度話し合おう? ね?」
ごめんなさい、もうあなたに用はないんです。
言おうとして言えなかった言葉であるが、それを伝えなければならない必然も、もうなかった。
その夜、金城は少し泣いたが、田口はひょっとしたら、そのことを知っていたのかもしれない。
「さようなら」