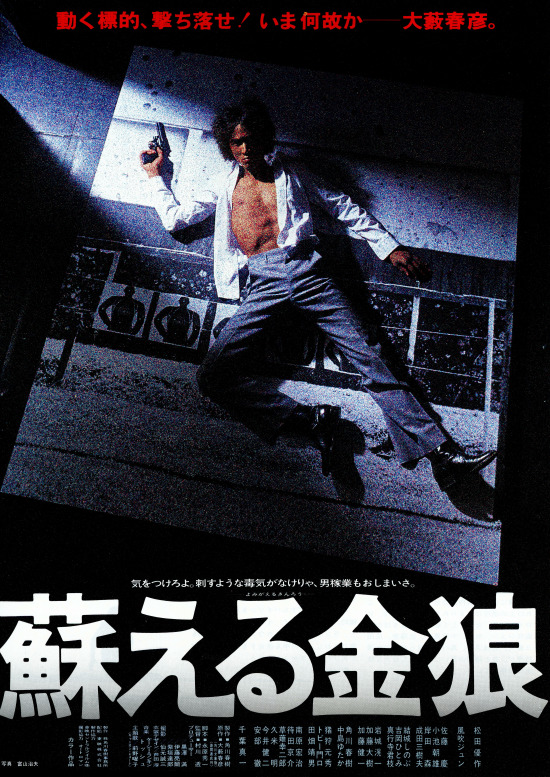やがて1961年に、当事映画界内でも「映画のためなら金は惜しまず」で知られた、永田ラッパこと永田雅一氏率いる京都大映が、予算を惜しみなく投入した超大作『釈迦』において、高山氏は特撮映画美術に初参加。
また、東宝教育映画の作品でも、セットやミニチュアを作り続けていた。その過程で、懇意になった漫画家のうしおそうじ氏の為に、うしお氏が設立しようと奮闘していたピープロダクションの発起人として名を連ねることになった。
そのピープロの処女作『マグマ大使』(1966年)の造形スタッフで、『大怪獣アゴン』(1964年)の監督・造形でもあった大橋史典氏と知り合い、高山氏も怪獣造形の道へと、どんどんと突き進んでいくことになる。大橋氏もまた、日本特撮の怪獣造形家としては、いつか語らねばならない存在ではあるが、あくまで『光の国から愛をこめて』はウルトラ評論であって、うしお氏や手塚治虫氏などと共に、日本特撮黎明期や、円谷英二監督を語るためには欠かせない存在ではあるものの、どうにも、語れるチャンス(や引っ掛けられるお題)に恵まれなくて現在に至っている。(本当なら、戦前にはターザン役者としてならした大橋氏が、『キングコング』(和製時代劇版・1938年)で、自らが制作したコングの着ぐるみに入って、映画の中で縦横無尽に暴れまわった豪傑な逸話(笑)や、円谷英二・手塚治虫・うしおそうじという三人の「戦後児童文化を支えた天才」の、親密かつ数奇な関係などを、いつか語りたいと思っている)
日本特撮界の黎明期という意味では、撮影現場ではない視点・地点から、様々な会社に関わり、作品に関わっていたという意味で、実は誰よりもキーパーソンとして機能していたのが高山氏だった。
高山氏のウルトラ初造形作品は『ウルトラQ』(1966年)のペギラだが、彼を円谷英二に推したのは、ウルトラでデザイナーとして雇われた成田亨氏であることは前項で触れたとおり。それを二つ返事でOKを出した円谷監督であったが、実は円谷監督は成田氏に推される前から、1963年によみうりランドで行われた水中バレエにおける、高山氏の美術に着目していて、また、円谷監督はうしお氏を介して大橋氏とも懇意な関係であったので、大橋氏経由で、高山氏のセンスと技術を聞いていたという前提があったのだ。
ウルトラの外でもまた高山氏は、うしお・大橋両氏とも密接な関係にあり、それぞれが運営するピープロと日本特撮株式会社が制作した『スペクトルマン』(1971年)『怪獣王子』(1968年)に参加する一方で、『ウルトラマン』放映開始の1966年には、本籍地でもある大映の怪獣映画『ガメラ対バルゴン』で劇場用怪獣を始めて造形担当。(大魔神を怪獣と呼ぶべきかどうか迷うところではあるが、この記述にした)60年代後期の大規模リストラで、円谷を追い出されたスタッフが集結して作った日本現代企画制作の『シルバー仮面』(1971年)で造形を提供する一方で、本家・円谷でも1972年、円谷プロ10週年記念作品だった劇場用映画の『怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス』で登場する三体の怪獣を造形し、テレビでも『アイアンキング』(1972年)『ファイヤーマン』(1973年)では、全話の怪獣を造形するなど貢献を続けた。
また、ユニオン映画で製作された『突撃!ヒューマン』(1972年)では、ウルトラ以来の成田亨氏との名コンビぶりを見せ付けるなど獅子奮迅の活躍ぶり。70年代中期には、狂騒的な群雄割拠の様相を呈していたキャラクター番組界において、『スペクトルマン』の宇宙猿人や『怪傑ライオン丸』(1972年)の主人公・ライオン丸など、常にそこで登場するキャラクターのクオリティを引き締める存在として、高山氏の造形物は機能していた。
およそ60年代黎明期以降、70年代までの怪獣特撮ドラマ文化史は、高山氏を抜きにしては語れないと言い切っても良いのではないだろうか?