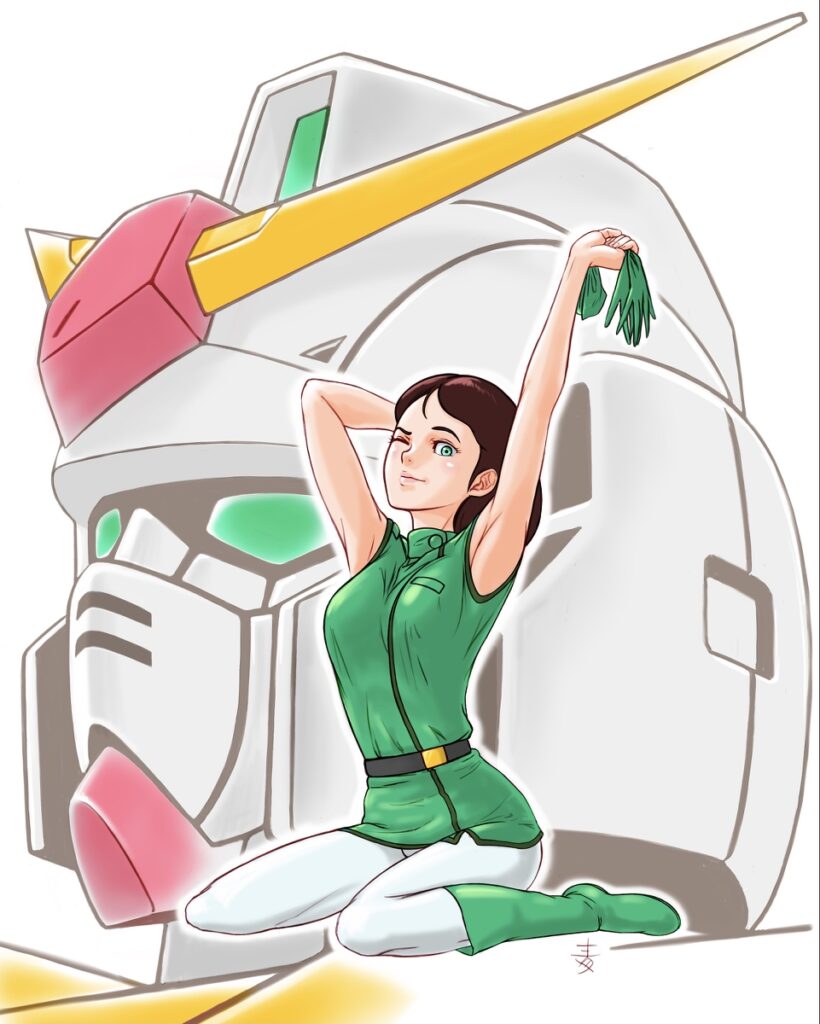しかし高山氏の場合は、むしろ成田氏と違っていたのは、後年、およそ自らの功績が考古学的価値を持つほどに注目を浴びてもなお、高山氏自身が、自ら当事を振り返ってあれこれコメントや著書を残す行為に傾倒したわけでもないという部分がある。周囲が知りたがる「当時」を振り返り、著書やインタビューなどを通じて記録や想いを後世に残すというのも、これはこれで大事なスタンスではある一方で、これだけ日本の特撮ドラマ界に、多様な方向から関わってきた功労者が、あえて口を閉ざしたまま、人生を駆け抜けていかれたというのも、それはきっと「芸術家は作品でしか語らない」という側面も含めて、筆者のような若輩者からしてみたら、ただただ敬服するしかないスタンスなのである。
それゆえに、あの時代に高山氏が何を思って、怪獣という奇形の化け物を製造し続けていたのか、また、氏が関わり続けたこの世界は、氏から見てどう写っていたかを、残された我々が知る手がかりは本当に少ない。
80年代に、特撮雑誌『宇宙船』(朝日ソノラマ)が連載していた高山氏の日記は、あくまで怪獣造形当事の日記を再録したものに過ぎず、それはもちろん、資料的価値は存分にあるものの、高山氏の「人と成り」を解読する手がかりとしては心もとない。また2005年にGyaoで放映されて、その後TLIPから発売された『怪獣のあけぼの』と題されたドキュメントDVDは、造形家としての高山氏の功績を存分に窺い知れる構成で興味深く視聴したが、しかしそこでの主観はあくまで、そのドキュメンタリーを統括した実相寺昭雄監督のそれであり、高山氏の体温を描いたとは、あまりいえない内容であった。
ネット上でのwikipediaなどの記述を見ると、高山氏が愛妻家であり、その生き様には義と縁を大事にする人間性が伺われ、そこには、前衛芸術と怪獣という異形の存在の具象化に人生を捧げたイメージとは逆の、人間らしさと優しさと、野太い気骨が伺える。
高山氏のエピソードで、筆者が最も敬服したのは、怪獣造形時代の多忙を極めた中、氏は手伝いに訪れたアルバイトの美大生に対して「これはね、生き物を作っているんだから、そのことを忘れないように手を入れてね」と、必ず念を押して作業にかからせていたというもの。
「作る時、子どものこころにもどって、目を閉じて、イメージを描くんです。どうしたら夢の多いものができるか。背中のトゲ一つでも、愛情をもって、たん念に作らなくては、子どもが喜んでくれません」(『ピープロ特撮の映像世界』朝日ソノラマ・1980年)
これは後年、高山氏が語った怪獣造形美学である。
「子どもに夢を」そう簡単に言ってのける関係者は多かったが、高山氏の仕事は、直接見える形になって筆者達の少年時代を彩っていた。後年「子どもに夢を」と語る子ども文化関係者の台詞の中には
作品を振り返って再読すると、疑問を感じるケースも少なくないが、高山氏の場合、その姿勢はそのまま、ゴモラやレッドキング、ケムラーの息遣いや、氏独特の、そして氏の作品にしかない「生命力」によって「子どもに夢を」という言葉に、無比の説得力を生んでいた。
高山氏の子ども好きは有名で、ウルトラの怪獣デザイナーとしては成田氏と並んで、輝かしい功績を残した池谷仙克氏が、ウルトラの後、高山氏と個人的に付き合いをしていた頃、お子さんが高山氏から、手作りの機関車玩具をプレゼントされたという逸話がある。池谷氏はその件に関して「もう壊れてなくなってしまったが、息子に渡さないでそっとしまって置けば良かったと後悔している。それは美術館に飾れるような、作品といえる出来栄えだった。その時息子に渡さなかったら叱られたであろうが、今思うと残念である」とコメントしている。
その手作り機関車玩具もきっと、高山氏が生み出した一つの怪獣だったのかもしれない。