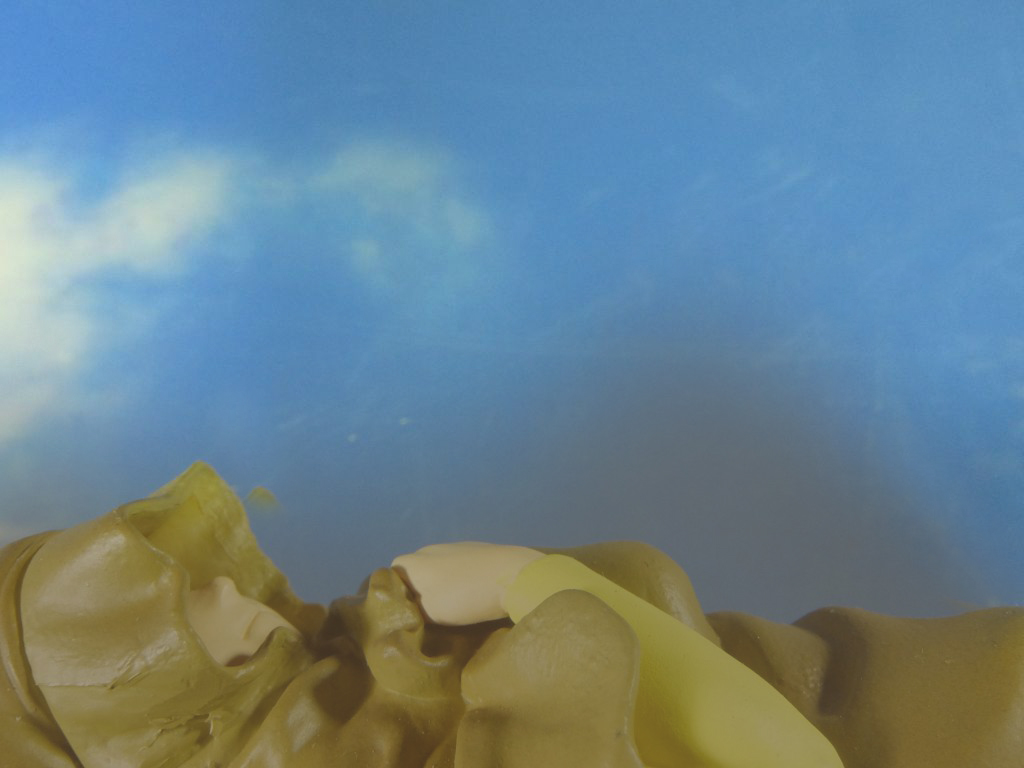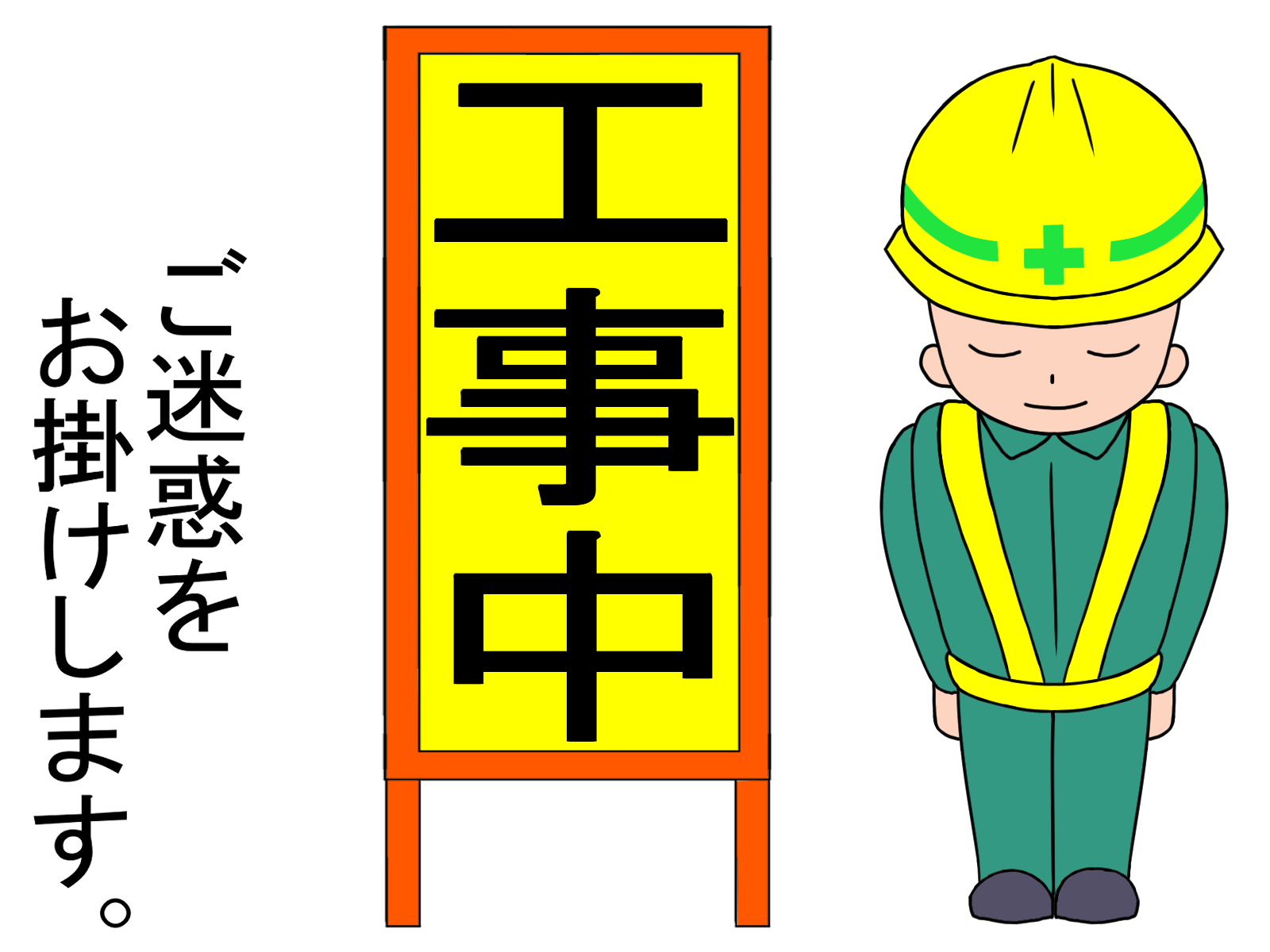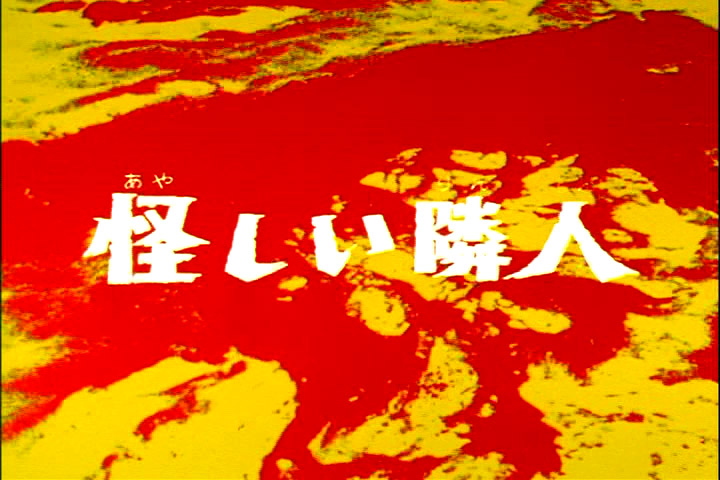フラウ「みんなが、あなたのこと、いつまでも心配していると思ったら大間違いよ」
アムロ「お前こそ、ジオンの連中に掴まったりして」
フラウ「……さっきの女の人が見てたから、私と手を繋ぐのやめたんでしょ」

『ガンダム』を映画にまとめるということ
その上で、およそ20年経ってから、富野監督は当時を振り返ってこうも語った。
富野 TVのダイジェスト版であろうが、映画になりうるだけの質量を持っているんだ。それを映画屋さんにわかって欲しいと思ってやったことです。だから『ガンダム』の3部作は最初、当時の映画屋さんのセンスで言う“TVアニメ”を映画で見せてあげるんだから、お前ら1本のダイジェストにまとめろという話もありましたけれど、それは拒否しました。つまり、まとめられるレベルにしかまとめられないし、お前らが思っているほどロボット物は甘くないんだぞと。そういう考えで、まず一本目をまとめた。「え、ここまでですか?」「だって、どこ切れました?」「どういうことなんですか?」「後2本作るんですよ。そうしたら何とか全部まとめられます」それが『ガンダム』3部作なんです。それをやってみせたことに関しては、反省なんかしていません。ただ、どうせなら全部作画をやり直すぐらいのことはしたかった。それを出来るだけの力がなかったのが残念ということではありますけども、興行そのものに関しての嫌悪感は一切ありません。
キネマ旬報社『富野由悠季全仕事』富野由悠季インタビュー
そこには、劇場公開当時、徳間書店の『ロマンアルバム エクストラ 42 機動戦士ガンダム』での、高畑勲監督が富野監督との対談で語った以下の部分。
高畑 なるほど……。ぼくは『ヤマト』に舛田利雄(註・1)さん、『地球へ…』で恩地日出夫(註・2)さんを起用したということをきいただけで、ああ、事大主義だなァって感じただけで、それ以上も以下もこだわりはありませんが。
(註・1 舛田利雄 『錆びたナイフ』(1958年)『花と竜』(1962年)『嵐を呼ぶ男』(1966年)をはじめとして、石原裕次郎など主演の日活アクション映画黄金期を支えた巨匠実写映画監督。アニメ映画『宇宙戦艦ヤマト』(1977年)の総監督を引き受けた後、80年代以降は『二百三高地』(1980年)『大日本帝国』(1982年)等、戦争映画の巨匠になる)
(註・2 恩地日出夫 『伊豆の踊子』(1967年)『恋の夏』(1972年)など、恋愛ロマン映画を得意とする巨匠実写映画監督。『傷だらけの天使』(1974年)『赤い迷路』(1974年)などのテレビドラマも手掛ける。竹宮恵子原作のアニメ映画『地球へ…』(1980年)では監督に就任し、原作にはなかったラブストーリーや戦闘シーンを大幅に増やしている)
という発言が内包している「実写映画と、そこで名を馳せた大監督様達に対する、テレビアニメ屋のコンプレックス」と、「そういった『テレビ漫画なんてものに、映画という崇高な冠をあたえるのであれば、せめてきちんとした本編(映画界用語で劇場用映画のこと)監督を、飾りで良いので名前借りでもしなければ』というプロデュースしか出来ないアニメ映画の商売的統率者達への不快感」を、この時期のアニメ監督たちは一様に抱いていたのかもしれない。
記者会見での「是非とも一本にというのなら、監督を降ろさせてもらったと思います」発言も、この時期、数多くのテレビアニメの名作が、実写映画の監督の名のもとに、ずたずたに切り裂かれて、原形をとどめぬ姿で2時間の尺に無理やり納められた「劇場用映画版」ビジネスの帰結を、既に知っていたからだろうと思われる(実際、テレビ版を富野監督がディレクションした『海のトリトン』(1972年)が、1979年に西崎義展氏プロデュースの元、再編集のみで映画化されたが、舛田利雄監督の監修名義が冠せられていたこともあって、富野監督は完全ノータッチで終わっている)。