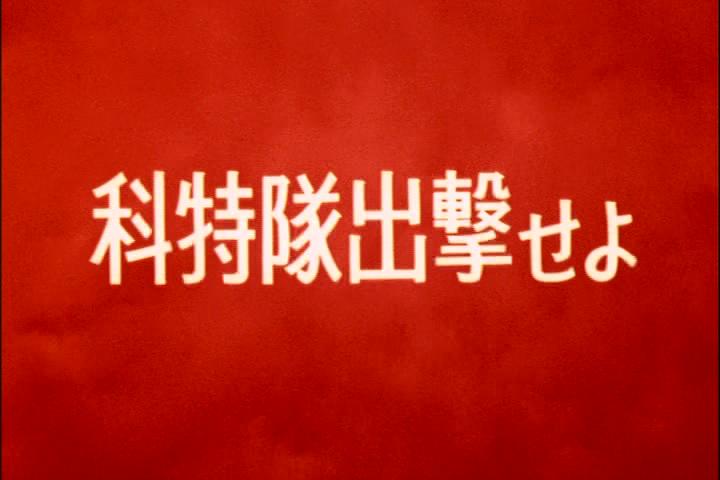前回『山際永三インタビュー 第六夜「山際永三と子役選びと『サンキュー先生』と」』

――80年代の中ごろから、監督は現場から遠ざかっていかれたわけですけど、それまでの間、監督がテレビの最前線で訴え続けてきたことへの、手ごたえのようなものは、どの辺にありましたでしょうか。
山際 僕の知り合いの弁護士さんが、僕をからかう時があって、「大人になって、ウルトラマンシリーズを観ているときに、やけに教訓的だなぁと思うと、必ず山際永三監督なんだ」とね(笑) 要するに、教訓をやろうとは思ってないんだけど、ちょっとメッセージ性があるっていうんで、そういうのが、子どもたちに吸収されていっていたということに関しては、僕は確信を持っていましたね。まぁ、僕も自分の全てを総括しているわけじゃないんだけど(笑) 僕は新東宝時代に、石井輝男さんに師事していたんだけれども、石井輝男さんにも、僕は惹かれるものがあったんですよ。どっちかといえば、ヨーロッパ映画の社会派映画が好きで、僕なんかは、映画の世界に入っていったんだけども……。例えば日本映画でいえば、今井正さんのああいう作風は僕、は嫌いなんですよ。お説教じみてて、社会問題だなんていってるけどね。たいしたことねぇじゃねぇかと(笑) 僕なんかは嫌いなんですよ。今井正批判もやったし、まぁ社会へのメッセージと言うけれどね。でも、政治的なものに、芸術が無力であることは、最初からわかりきっていることで。むしろ芸術的なことを追求していけば、政治的な面では無力であり、かつ反抗的でね。政治からはパージされていくというというのが芸術家の運命だと。
――監督が以前お書きになった文章で、アール・ヌーボーの画家、アルフォンス・ミュシャの、民族運動に関する論評を読ませていただきました。
(以下筆者引用 山際永三監督の談話より)
非常にポピュラーなアール・ヌーボーの画家アルフォンス・ミュシャは、パリやアメリカで大成功をおさめたあと、故国チェコ・スロバキアに帰って大歴史画に取り組んだのだが、不評に終わったという。
その歴史画は、チェコ民族の古代から伝わる多くのエピソードを、市民ホールの壁や天井に描くもので、その取材だけでも大変だったらしい。
私は、実を言うと、この5月15日のNHK『新日曜美術館』を見ていてそのことを知った。
番組のなかでは、すでに独立を達成した(1918年第1共和国)後のチェコの人々にとって、ミュシャの民族主義はアナクロニズムにみえたと説明されていた。
しかし私たちは、その後のチェコの独立とはほど遠い苦難の歴史を知っている。第2次世界大戦が終わったあとでさえ、チェコは戦車に蹂躙されている。
ミュシャ晩年のチェコ独立が、あだ花でしかなかったことは確実だ。
10年ひと昔というが、歴史の意外な展開と、それに拮抗する作家・知識人の運命というものは、技術・方法論の成否をふくめて複雑極まる。容易なことではない。
この10年、日本は世界でもあまり例のない独特な閉塞感を増幅させた。
ナチスのように黒シャツ青年団の1群が街を闊歩して、ユダヤ人狩りをするというようなところまでは、まだいっていないものの、タバコ・空き缶ポイ捨て禁止の条例化とか、防犯カメラ(Nシステム)の多用とか、日の丸・君が代強制とか、青少年健全育成法案とか、いよいよややこしくなっている。
こういう傾向になる契機は、1995年のオウム事件にあると言う論者が多いし、確かに、その後のアメリカ同時テロ事件、中東における戦争とともに、日本社会に対して深い影響を与えたことは事実だ。
しかし私は、その95年のさらに前の10年に着目すべきだと考えている。
80年代前半に、マスメディアの系列化完成、新聞に対するテレビの優位によって、日本国民を対象にした、いわばマインドコントロール状況とも言うべきものが現出し、80年代後半からは、警察レベルで保安部が生活安全部に衣替えし、警備・公安本位からのシフト変更がなされた。
官僚の世界ではバブル崩壊に備え様々な分野で、いわゆる中坊公平体制とも言うべき、いかにも世のため人のためを装う方針が貫徹されていった。
それらを総合すると、今日の閉塞状況、柔らかなファッシズムは、20年前から仕組まれていたとみるべきなのだ。
協同組合日本映画監督協会70周年記念事業実行委員の1人である伊藤俊也監督が、かつて理事会の席で「映画監督という職業は、殆ど気違い沙汰だ」というようなことを言って、皆を笑わせたことがある。
アルフォンス・ミュシャの生涯を考えているときに、ふとこの伊藤さんの言葉を思い出した。
ものすごくまともな幻想世界にのめり込んだミュシャ晩年の孤独。それに耐えて彼はその後の20年を見通していたのではあるまいか。
映画は、なおのこと時代の産物である。
監督は、孤独のなかで、映画監督の著作権確立を求めて、彼方の連帯を模索する

山際 だから僕は、そういう意味では政治主義が大嫌いでね。僕が思うに、狂気、狂気っていうものが、人間の本質的な力であって。それはまぁ皆、なんとかコントロールしながら、この日常生活を送っているわけです。狂気が基になっているというようなことを考えると、石井さんの映画にも共通する物があると思うし、石井さんから学んだこともありますね。自分でも、あまり意識はしてなかったのだけれども、僕は政治的には、そういうアナーキーな、いかなる政治体制に対しても、いつも絶望するアナーキストという立場だし。
――特定のイデオロギーに属しているわけではないと。
山際 映画に狂気を求める、ということをしてきたつもりなんで。ウルトラシリーズなんかは初歩的な、ごく常識的な、オブラートに包んだような物だけれどもね。子どもたちにはそれは、必ず伝わっているという意識は持っていますね。ところがその、それこそ80年代に入って、子どもたちがもう『俺はあばれはっちゃく』(1979年)を観ないで、『西部警察』(1979年)を観るわけですよ。それで、刑事が銃を撃って、自動車が燃えたりするのを面白がってるわけ。こりゃあいかんと思ったわけです。『俺はあばれはっちゃく』っていうのは、山中恒原作なんだけれども、ガキ大将的なものを描いているんですよ。あんなものは、70年代後半でも、受けるわけないんじゃないかと思いましたよ。ファンタジー的設定があるわけでもなく、ごく当たり前なね。まぁあえていえば、小学校5年生で、クラスにアイドルの女の子がいて、毎回その子に惚れこんじゃ、馬鹿にされてるみたいな(笑) 学校の教室の中に、そういう擬似恋愛的なものを持ち込んでるという、そういうところが、新しいっていやぁ新しいかなと。それが受けたのかなと思いましたよ。

――あの番組は、観ている子ども達は皆、等身大的に観ていた気がします。
山際 それがまぁ、ややトレンドかなと思うんだけど(笑) 結局、九重佑三子版の『コメットさん』(1967年)をやった僕としては、大場久美子の『コメットさん』(1978年)が嫌なんですけどね。本来コメットさんは「宇宙の学校の落第生」。それでコメットさんが下宿する家の二人の男の子は「地球の小学校の落第生」で、勉強が大嫌いという。これが主人公だったところが、いいところでね。大場久美子の(『コメットさん』)だと、ぜんぜん優等生なんですよね。