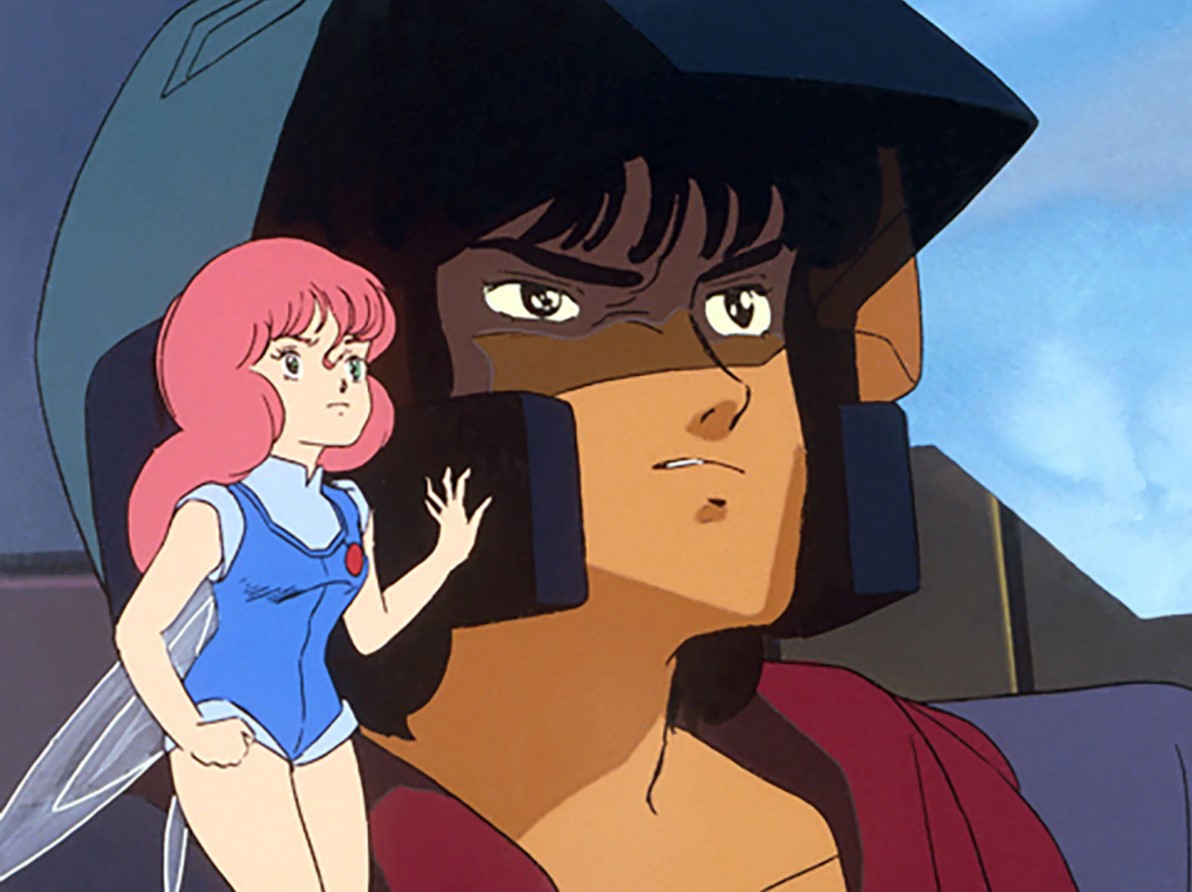『マイナス・ゼロ』と『エロス』
まずは『マイナス・ゼロ』その物語はこうだ。
昭和の高度経済成長期を始まりの舞台に、そこで偶然、未来人の残したタイムマシンと出会った主人公・俊夫は、そこで少年期の戦時中からタイムトラベルしてきた、当時の「憧れのお姉さん」啓子と共に、タイムマシンをいろいろ検証していくうちに、タイムマシンに運命を翻弄されるがごとく、そこからさらに、現代や大正時代末期など、何度も過去と現在とのタイムスリップを繰り返した果てに、やがて俊夫は啓子と離れ離れになってしまう。
結局、自分の少年時代でタイムマシンを失うことになってしまった俊夫は、その過去の時代で生きていくことになるというもの。
一方『エロス』はこうである。
現代(小説発表当時)を代表する女性シャンソン歌手(読みさえすれば、モデルが誰なのか、昭和世代であればすぐ特定できるが)が過去を語る。田舎から東京に出てきた、昭和初期の少女期。
その過去を思い出して語っていく中で、語られることのない「あり得たかもしれない、もう一つの過去」が、小説の構成の中に割り込んでくる。イマドキのアニメやゲームで言うところの「フラグ分岐」である。要するに1970年代に「一つの流れの小説」として、大きなフラグ分岐をした二つの物語が並行して描かれる、『火吹山の魔法使い』構造のようなSF小説があったと思えばよい。「現在」「過去」「もう一つの、ありえなかった過去」の、三つの流れの中で、少女時代のヒロインと、その少女を愛した真面目な青年との、恋愛の行方が交錯していくというもの。
広瀬文学を構成する三つのガジェット
精密機械の如しの、構成力と構造力
広瀬氏は、まだジャズバンドとしても、SF作家としても食えなかった時代、クラッシックカーの模型を組み立てる仕事で食いつないでいたと聞く。
当時の高級模型は、イマドキのガンダムのプラモデルとは違い、無数の細かいパーツを、1mmの狂いもない中で組み立てていき、完成させるだけの、器用さと技量、根気と俯瞰感覚、ハイレベルな完成像の把握力が求められる。
広瀬氏は、その力を小説という「文字という記号を並べる作業」に、惜しみなく注ぎ込んだ。
一言で言ってしまえば、『マイナス・ゼロ』はタイムマシンSFであり、『エロス』は(読者の思い込みを覆すどんでん返しを仕込んだ)並行世界SFであり、『ツィス』は(ある意味で、小松左京氏が『首都消失』『こちらニッポン』等で手掛けた)社会シミュレーションSFなのだが、そこではまず、文学性よりも、トリック、ギミック、伏線、ディティールの整合性が重視されており、それらがクライマックスに連結していく過程を以て、なみなみならぬカタルシスを得られるというのは変わりがない。
取材力・調査力・再現力
『マイナス・ゼロ』星新一氏の解説によれば、広瀬氏は『マイナス・ゼロ』で「正確な銀座」を描写するために、自分が少年時代の銀座の街並みや店の並び、景色を、全て調べつくしたという。まだネットどころか、住宅地図さえなかった昭和初期の銀座をだ。しかも、『マイナス・ゼロ』では、決して銀座という街と景観は、物語のメインガジェットではないにも拘らず、自分の憧憬を再現するためだけに、ディティール部分でそこまでやってみせてしまったのだ(広瀬氏存命中に、『八月の濡れた砂』(1971年)等で知られる、日活の鬼才監督・藤田敏八氏による映画化が企画されたが、当時の映画予算規模で昭和初期の銀座を再現できることが不可能だと判断されて、お蔵入りになってしまったという。それから20年近く後「まさに、昭和初期の銀座を、CGではなく1/1セットで丸ごと作ってしまった」実相寺昭雄監督の『帝都物語』(1988年)等を思うと、とても惜しかった企画だと言わざるを得ない)。
そして、その緻密な調査力によって、広瀬氏によって掌の上で操られてしまう、読み手のこちらの「金銭感覚」。ここは些細な要素と思われるかもしれないが、実は大きな影響力を持つ。
あなたが今すぐネットでWiki等で調べられるとして「昭和初期の1円が、現代の貨幣価値でいくらぐらいなのか」を、感覚としてすぐ察することはできるだろうか?
もちろん、それは無理なのは承知の上なのだが、広瀬氏の完璧な調査力が、逐一作品内で、しかもさりげなくディティールの積層で表現されていくと、そこで広瀬マジックにかかった読者は、いつの間にか「ふーむ。これで5銭か、ちょっと高いな」とか「これで1円もするとは、当時の庶民には酷な話だ」とかを、本当に自然に、作品内部の登場人物たちと共有できるのだ。
このディティール主義は、深夜アニメの裏設定などとは明確に違い「本当に『そこ』にあったこと」へのこだわりであり、その元時代を知る者にとっては、重要なジョイントとなり、元時代を知らない者にとっては、重要な「想像への踏切台」として機能するのだ。「事実というディティールの積層」は、SFという突飛な綺譚を楽しんでもらうために、戯作者が忘れてはならない基本構造だと思い知ろう。
未来宇宙SFがフィールドであっても、数式と理化学が、市政の読者と宇宙未来世界を繋げてくれるロジックと、それは圧倒的に等しい。
また『マイナス・ゼロ』内だけでも、ダットサンの発売開始や神宮球場水原リンゴ事件(昭和8年10月22日)や白木屋デパート火災事件(昭和7年12月16日)等実際の昭和初期での出来事を、上手くフィクションの中で、謎を考えるフックや、劇的に人間関係を変え、推理の鍵をつかむガジェットとして有効に活用している。この手法は、昨今の伝奇綺譚やタイムトラベルジャンルでは当たり前だが、工学部で建築を専攻し、模型とジャズという、全てが「精密なパーツが寄せられて、一つの完成形を生み出す表現」で構成されていた広瀬氏の才能は、この物語において、究極に発揮された。
登場当初は、単純なタイムマシンだと思われていた機械が、それを使って(主人公の興味本位の)様々な実験を通じていくうちに、予測不能な不確定要素やアクシデントを次々に巻き起こし、人物関係もどんどん交錯していった混乱の先で、物語の最後の20ページで、全ての謎と伏線が繋がり、それまでのあらゆる不確定要素やアクシデントは必然であり、ラストシーンに至るまでに必須な要素だったのだという帰結を見る時、その構成力は、この取材調査力がなければ、バランスを欠く核でもあったのだ。
人間の、変えることが出来ない運命を、変える天使
時代劇歴史小説家の司馬遼太郎氏が、『広瀬正全集』の『ツィス』巻末の解説に寄せた文章で、自身が選考委員を務めた、第66回直木賞選考における『エロス』論評について、以下のように書き記した。
私は広瀬正氏の『エロス』を推した。深読みかもしれないが、愛というこの人間現象に奇妙な衝撃力をもつものを、作品は科学的物質としてそれを抽出し、合成し、それをこの小説に登場する数人の人間の過去に対し、実験的に添加した場合、「過去」がどのように変化をおこすかということをSF風に考えてみた文学であるように思える。この小説に使われた人間も空間も時間も、フラスコや試験管といったふうの実験器具として組み合わされ、作者自身は白い実験衣を着た進行係に過ぎず、実験の進められようが非現実的であっても、遊戯としてわりきってしまえばじつにおもしろい。この作品は『マイナス・ゼロ』『ツィス』につづいて、三度目の候補作である。このあまりにも現実離れした遊びの世界は二作ともおおかたの共感を得ず、こんどもそうであった。『エロス』は前二作とくらべてやや広瀬的世界の濃度が薄かったのが物足りなかったが、しかし才能(広瀬氏のは従来の文学的才能ではなさそうである)という点では、私は三作とも頭が下がった。
『ツィス』巻末解説 司馬遼太郎