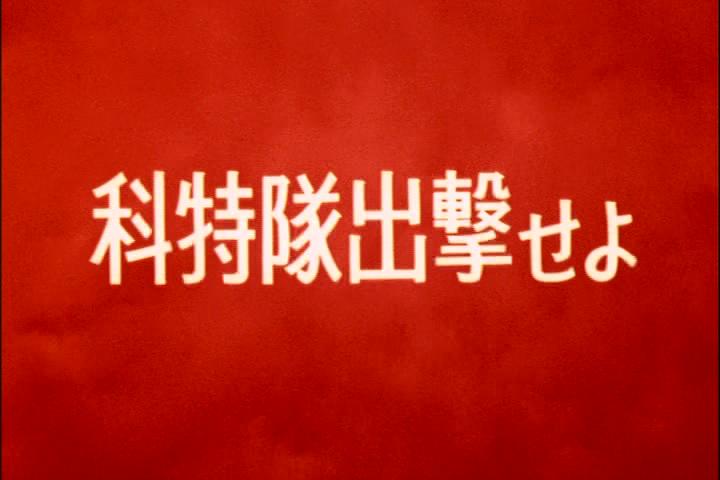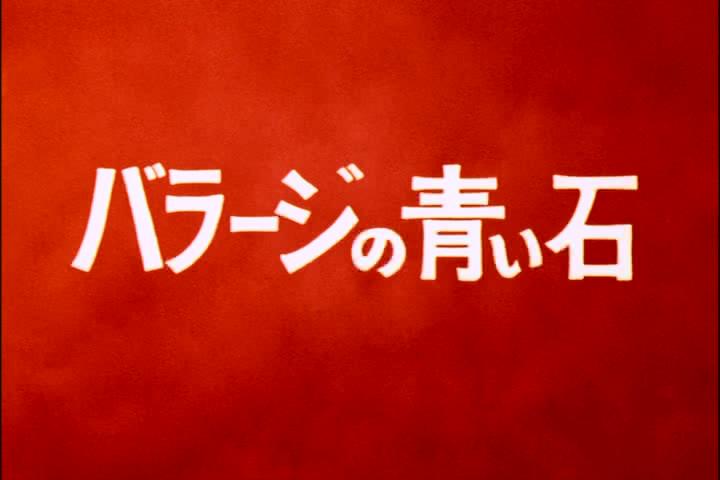『ゴジラ』(1954年)に端を発した怪獣という存在には、様々なアイディンティティが盛り付けられた。
例えば、その始祖であるゴジラは、太古の恐竜が放射能によって突然変異し、まさに荒ぶる神として生まれ変わったという存在である一方、かつて90年代に発行された別冊宝島の『怪獣学入門!』において、赤坂憲雄氏が展開した「ゴジラは太平洋戦争の英霊である」という解釈論は、当時俄然とした説得力を持って語られていた。
この、一方で大自然の驚異的生物という設定を表に持ちながら、その裏側では、人間の怨念や人類への憎悪を感情として持つという二面性は、その後、特に円谷プロ・東宝で描かれていく、スタンダードな怪獣に色濃く受け継がれていった。
第一期のウルトラ、しかも『ウルトラQ』(1966年)においては、しばしば怪獣は「現象」として捉えられ、その存在自体が、人類へのなんらかのメッセージを持っているという、寓話的な描かれ方をされてきた。
『ウルトラQ』のメインテーマは「大自然のバランスがもし崩れたら?」であることは有名ではあるが、つまり怪獣は大自然からのメッセンジャーであり、怪獣は人類への警告であるというケースが少なくはなかった。
宇宙も自然の一部であり、いやむしろ地球の自然は宇宙を包む広大な自然の一部でしかないのだと思えば、バルンガやケムール人、ナメゴンだって自然の使者だったのかもしれない。
そのQ怪獣の中で、ゴジラが持っていたもう一つの側面である「人間の闇や怨念が投射された存在」という怪獣は実は少なく、人間の醜い一面や怨念が怪獣出現に絡む作劇というと、一人の科学者の怨念が結果として、怪獣を出現させてしまうという『甘い蜜の恐怖』や、娘を死なせてしまった老人が大蜘蛛になってしまった『クモ男爵』など、金城哲夫作品の中に、僅かに現れているだけである。
むしろゴジラが持っていた、人の持つ怨念や魂が投射されている怪獣というのは、実は第二期以降のウルトラ怪獣に顕著であり、『ウルトラマンA』(1972年)に登場するヤプールの超獣や、『ウルトラマン80』(1980年)初期に登場する一部の怪獣などは、その登場理由に、明確に人の怨念の存在が組み込まれていた。
それまでは、映画館のスクリーンで、年に数回しか拝めなかった怪獣を、毎週毎週、違った形で送り出したという部分が、もちろん円谷プロのウルトラシリーズのエポックだったわけではあるが(ウルトラより先駆けたテレビ怪獣映画シリーズである『怪獣アゴン』(製作1964年・放映1968年)や『マグマ大使』(1966年)は、さすがに毎週新怪獣というわけにはいかなかったようである)、週一ペースで怪獣を生み出していかねばならないという責務は、様々な形の怪獣を生み出していった。
怪獣は外見上の形ばかりではなく、その存在理由、アイディンティティにおいてもまた、ありとあらゆる方向から存在の因数分解が行われ、そこで抽出された要素が拡大表現されることで、怪獣のバラエティさをかもし出すことが出来たのである。
本話に登場するギャンゴという怪獣は、そういった意味では、人の意思が込められたタイプの怪獣の典型であり、その流れは先述したように、ヤプールの超獣や80の初期怪獣などに受け継がれるが、本話は全体的にスラップスティックコメディに徹することで、そこで原因となった人間の心の闇の重たさやおぞましさを中和している。
「人間の意志や怨念が、生み出した怪獣」という路線で言えば、本作ではこの後、ヒドラ、ウーなどを生み出すが(少し違うがそういう区分けで言えばジラースやジャミラも含まれる)、そこでギャンゴと対を成すのがガヴァドンなのであろう。
本話でギャンゴを生み出す鬼田という男は、本話演出ではとても児戯性の強い男性として描かれている。
そこはもちろん「大人を子どもとして描く」演出の満田監督だからでもあるが、そこで「様々な欲望を持つに到った大人が、なんでも叶えられるという、ファンタジーな可能性を手に入れたときにどんな行動を取るか」という、本話の核でもある部分においては、鬼田はそこで「金・権力・女・ステータス」などといった、殆どの大人が、普通このような状況であればまず発想するであろう願望を排除して、まずは怪獣を生み出していたずらするという部分に価値を与えているのだ。
ここをして、ウルトラマンという番組なのだから、怪獣を出してもらわねば話にならないなどという無粋なツッコミをするのではなく(だったらそもそも、願いを叶える隕石など出さねばいいのだ。怪獣を出現させる手段だけならいくらだってあるはずである)、鬼田という大人が、なぜそこでの願望の筆頭に怪獣を選んだのか、そこを考察していくと、本話のウルトラマンにおける位置づけが見えてくるのである。
鬼田という男は、本話演出では、身体障害者として描かれている。
つまり、彼は被差別者であり、健常者が支配統括している、健全な大人の社会からはパージされたマイノリティであることが見て取れる。
先述した「大人が欲する要素」とは、大人が構成する社会の中において、初めて価値をもって輝くものであろう。
無人島に、たった一人で生きていく中では、金はただの紙切れだ。
社長や総理大臣の肩書きも、無人島では意味などない。
被差別者として、社会からパージされた一人の大人が持つ願望。
普通ならそこで、自身を健常者にして欲しいと願うのだろうが、鬼田は被差別者の視点から、健常者と健常者が構成する社会を見てきて、むしろ健常者とは唾棄すべき存在であると、痛感したからなのかもしれないが、本話では決して鬼田の口から「俺の脚を治してくれ」といった類の言葉は、最後まで放たれることはなかった。
その「現実社会を恨み唾棄し、一歩下がった場所から嘲笑する立場」に、自ら納まった鬼田という大人にとっては、一般社会の普通の大人達が望むどんな欲望よりも化け物を生み出し、操り、社会を混乱させること、その方がよっぽど魅力的だったのではないだろうか。
怪獣はもちろん、被差別者の象徴として描かれることが多かったが、現実社会の人間のマイノリティは、個人ではただ差別される側に立ち、排他されて存在そのものを消されてしまうことがしばしばあるが、怪獣という存在は圧倒的な存在力と行動力で、無数の「普通の存在」達に向かって脅威を与える側なのである。
それこそが、金よりも女よりも鬼田が望んだ願いだったのではないだろうか。
(余談だが、本話が決して「大人ならではの欲望」の存在自体を否定していないことは、本話序盤で青嶋幸男氏が望んだ「本当に欲しい物」が「お嫁さん」であったり、鬼田がホテルの部屋で金やごちそうを望もうかと迷うあたりであったりを見れば、これはもうあきらかであり、ギャンゴ出現はスタッフの確信犯であると断言できる)
「真に排除された者に最後に残るものが少年性である」
これはもちろん、初期ウルトラのメインライターであった、金城哲夫氏が常に秘めていたテーマであることはこれまでにも何度も解説済みだが、はたして、そんな鬼田の怨念を受けて登場したギャンゴは、まさにいたずら小僧といった振る舞いで暴れるだけで、そこには決して、被差別者が持つ湿っぽい憎悪は見られなかった。
ここには、初期ウルトラの全作家・作品に通ずる「怪獣=子ども=社会からパージされし者」という図式がみてとれる。
それは例えば、金城氏における「怪獣と孤独な人間の閉じた関係」を、成立させる大切な要素であったりもしたわけで、後年大人社会は必死になって「なぜ子どもは怪獣を好むのか」を解析するが、何を隠そう、そもそも作り手側にとっては最初から、怪獣と子どもは同根に存在していたのであった。