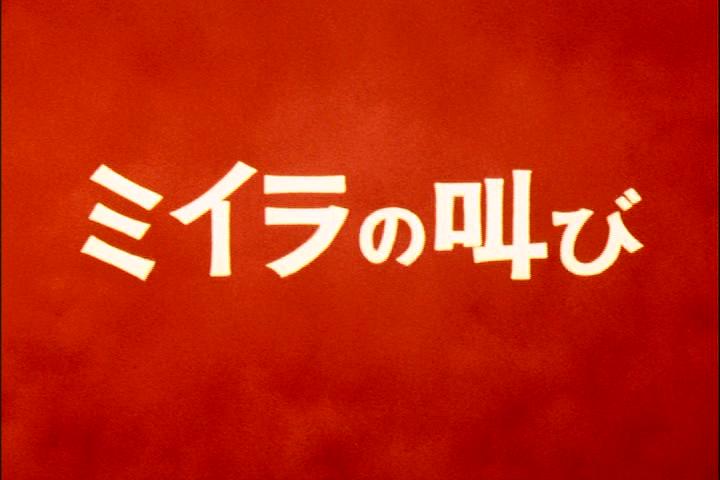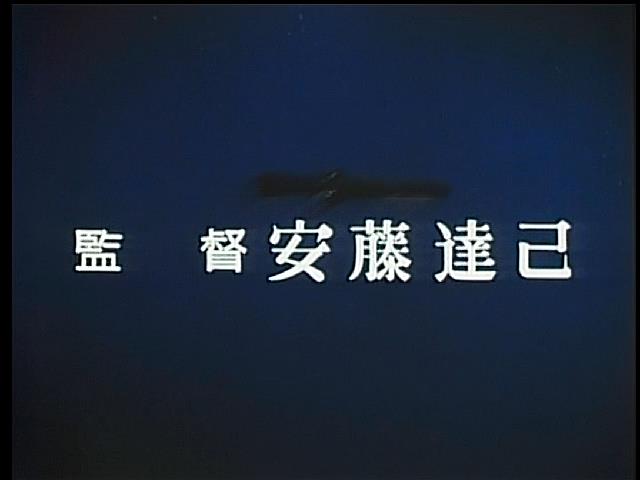しかし、ここで冷静になって考えてみたい。
この前後編を俯瞰して見渡してみると、そもそもここで、ペダン星人が偽りの正論を振りかざしてまで、ダンの前に正体をあらわにして登場する必然性が、実はどこにもないのである。
そこでのペダン星人のペテンは、一見地球侵略上での駆け引きのように描かれるが、実は、そこでの会談でドロシーがダンを騙し通せてたとしても、ペダン星人戦闘機群が発見されれば、ペダン星人の真意は見抜かれるわけで、実際劇中でも戦闘機群の発見と共に、ペダン星人の野望は全容を現すのである。
むしろ本話を、前編解説でも語ったような「当時流行していた、スパイ物要素を取り入れた、完全娯楽編」としてプランニングするのであれば、「拉致されたドロシーをウルトラ警備隊が潜入奪還して、キングジョーと決戦する」というような箱組の方が、よっぽど「それらしい」のである。
ならなぜ、金城氏はそういったシーンをわざわざ入れて、木に竹を接ぐような真似をしたのか?
それは、前編の物語のルックスに込められた、『故郷は地球』との、奇妙にして確信犯的な符丁を認知したときに、金城氏の呻きのような思いを掬い取ることが出来るのである。
「地球人の宇宙開発」という原因で起きた、「世界各国から集まる、会議要人へのテロ事件」の勃発。
「万国旗はためく会議場へ迫る怪物を、光の国の超人が食い止める」というクライマックスに至るまで、その基本構造は『故郷の地球』のドラマ展開を、なぞるように全編が構成されているのである。
もちろん、これが偶然である可能性だってあるだろう。
今となっては、誰にも確認は出来ないのも事実。
しかし、全く異なったテーマを持ったはずの2作品が、そのテーマの外の、ドラマ展開の箱組とディティールの部分だけ、ここまで似通っているというのは、初期ウルトラ作品では珍しい。
それは、つまり本話が、テーマ的に『故郷は地球』へのアンサーなどではなく、『故郷は地球』がテーマの外に持っていた「結局ジャミラのやったことは許されるのか」の部分だけを抽出して、そこへ「揺るがない悪」という存在をはめ込むことで、『小さな英雄』ではフォローし切れなかった部分を、ようやく作品をまたいだセブンにおいて、補完したのではなかろうか。
例えば、佐々木守氏のドラマ脚本の一つに『ふたりだけの銀座』という作品がある。
『七人の刑事』(1961年~1969年)で放映された、刑事ドラマの一本であり、この作品と『故郷は地球』で共通する部分も多い。
ドラマは(既に前々回『故郷は地球』評論で解説したが)、夢を壊され絶望して、生きる希望も幸せも失った青年が、銀座の真ん中で、全く無関係な通行人を襲ってしまうという話だが、例えばこの話だけ見れば、視聴者は主人公の青年に感情移入してしまい、その結果起こされる「通り魔殺人」という犯罪に対し寛容になるだろう。
しかし、その情状とは別個に、犯罪は犯罪であり、その犯罪が明らかな悪意と共に起こされれば、そこには酌量の余地はない。
つまり本話は金城氏による、そういった視点・スタンスからの、アンサーでありバランス保持作品だったのではなかろうか。
そのことが、少し捩れた感覚で現れたのが、先ほど疑問を投げかけた違和感の正体である、ダンとドロシーの会談シーンなのであろう。
「宇宙人にも宇宙人の理があり分があり、正義がある」という、セブンで他作家により書かれ始めていたテーマに対し、金城氏はそれまでも必死に「宇宙でも地球でも正義は一つなんだ」(『宇宙囚人303』)と、ダンに語らせるなどしてバランスを保ってきたのだが、それが通じなくなっていく先を見越して、あらかじめ予防線を張っていたのではないだろうか?
それはある意味で、若槻的正義概念論や佐々木式価値観破壊に対する、頑なで駄々っ子のようなスタンスにも見えるのである。
結果、そのシーンは物語全体を破綻させて、正統派娯楽編であるべき本話に致命的な違和感を残した。