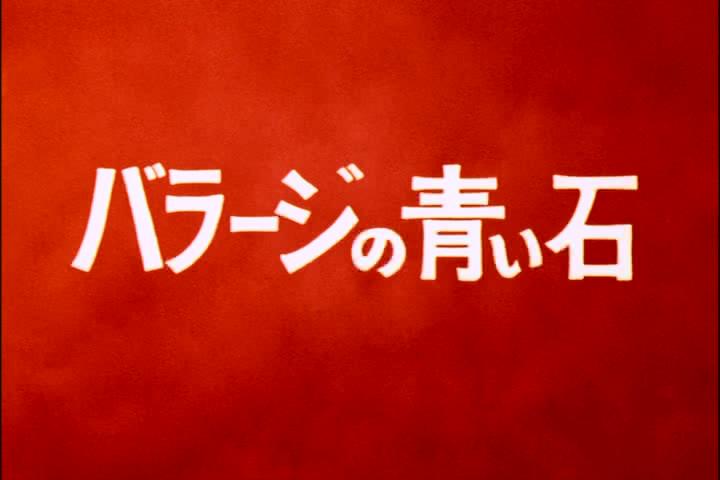本話の脚本・監督を請け負った、TBS映画部(当時)の飯島敏宏監督は、『ウルトラマン』(1966年)の頃は、少年向け科学雑誌や科学辞典を、常に枕元に置いて、暇をみつけては捲りながら、ネタ探しに勤しんでいたという。
ウルトラマンの疑似科学性は、各スタッフによる、そういった勉強があってこそ、当時の少年少女を魅了したともいえて、確かに今の目で見ると、稚拙な科学考証や科学定義の誤認が目立つかもしれないが、それは、正確な考証よりも娯楽優先、センスオブワンダーを重視したからであり、決して科学性を軽んじたわけでも、この時代の少年達が抱いていた科学への夢の軽視でも、どちらでもないことが、本話において非常に顕著である。
それは、宇宙ロケット時代の当時を逆反映した「おおとりの第2ロケット発火装置の脆弱性」をはじめとして、本話において随所随所に散りばめられた、パンスペースインタープリター、光波バリア、自動追跡装置、マルス133、テレポーティション、八つ裂き光輪などなど、溢れんばかりのアイディアと疑似科学性、単語の持つニュアンスや使い方に現れている。
ここで語られる疑似科学とは、怪獣映画の始祖『ゴジラ』(1954年)において、志村喬氏が演じた山根博士が、劇中でゴジラという生物に関して語った(当時判明していた地球生物史から見ても、明らかに間違いだった)、「今からおよそ200万年前、ジュラ紀から白亜紀にかけて極めて希に生息していた、海生爬虫類から陸上獣類に進化しようとする中間型の生物」にも相通ずると筆者は判断する。
そこでの「正確な学術的論証と、空想ドラマの中で語られた疑似科学性とが、明白な違いを持っている」という現実に関して、筆者は二通りの可能性を感じている。
一方には、既に解説したように「あくまで科学考証は、その正確性よりも、物語をより面白くするためのエッセンスであると割り切る」というようなスタンスが見えることは明白であり、なんら『ウルトラマン』『ゴジラ』の製作側が、科学や生物学というものに対して、不勉強だったことを表すものではないと言い切ってもよいだろう。
しかし、またその一方で思えるのは、あえて既存の科学・生物学とは違う学説や常識を作中で提示することによって、その物語世界が、テレビ(映画のスクリーン)の前の我々が住む世界とは、微妙に異なったパラレルワールドで展開されている寓話なのだと、それを、静かに主張しているようにも受け取れるのである。
この世界観ずらしは、ウルトラの元祖『ウルトラQ』(1966年)では、主に一ノ谷博士が担当していたが、もちろん『ウルトラマン』では、同じように科学者の岩本博士がそれを担う役割をもっている。
本話を担当した飯島監督と、ウルトラシリーズ以前のテレビドラマ時代から、『月曜日の男』(1961年)などでコンビを組んでいた脚本家・藤川桂介氏が、岩本博士を扱うに当たってそこで組み込んだルーティンワークは、その話で起きた事件や、残った謎の前で、あえて「人類科学の最先端を象徴する岩本博士」に佇ませ、口を閉ざさせることで、ウルトラマンが、我々人類が、どうあっても乗り越えることは出来ない、宇宙や自然の謎はあるのだと、そこを落としどころにした作劇を繰り返してきたわけだが、一方の飯島監督は、その「人類の科学」が進み行くべき道行きの先において、我々人類はどうあるべきかを、様々な角度から検証するドラマ作りが目立つ。
そして本話で最終的にポイントとなった「人が、自らが産み落とした科学と文明を、最後まで信用できるのか?」というテーマは、『ウルトラセブン』(1967年)でも『勇気ある戦い』などでも顕著であった。
(もっとも、そこには佐々木守氏による、例によっての「ちゃぶ台返し」もあるのだが)
『ウルトラマン』『ウルトラセブン』期の飯島作品は、その多くが、人類の発明した科学文明には、多くの脆弱性が含まれており、それを、単一的な楽観論と夢見がちな希望的観測だけで語ってはいけないが、だからこそ、危機管理と対応能力を養い、しっかりと地に足の着いた状態で、「科学」を灯火にして、未来と宇宙という未知の道程を歩いてゆかねばならないのだと、一貫したメッセージによって、作劇が成り立っているものが多い。
バルタン初登場となったエピソード『侵略者を撃て』もまた、バルタンという存在に投影された「科学文明の発達した、高度な文明社会であっても、たった一人の狂人によって、全てが崩壊することもある」が、地球人対バルタン星人という悲劇を生んだ根幹だった。
また、科学が生んだ核爆弾が、それを産み落とした人類の使用意図とは関係なく、地球を滅ぼす危機を呼ぶ『怪彗星ツィフォン』。人類が築き上げてきた最先端科学の海底基地が、一匹の怪獣のドリルの一撃だけで、一瞬にしてただの棺桶状態になって、存亡の危機に陥る『海底科学基地』や、「科学の最先端」という意味での象徴としては、『ウルトラマン』世界の疑似科学の頂点に位置するはずの科特隊基地が、一匹の怪獣の(破壊活動ではない)超能力によって、翻弄される描写をスラップスティックコメディ化した『無限へのパスポート』や、ダイアモード鉱石から作り出される、マグネリュウムエネルギーが、人類の科学によって作成できるかどうかが、地球の存亡を左右した『セブン暗殺計画』。さらに、既に評論を終了した『科特隊出撃せよ!』『ミロガンダの秘密』も含めて、飯島監督はどの脚本家とタッグを組んでも、常にそこには「科学と人間と、宇宙と未来」というテーマが内包されていた。
ウルトラファンにとっては、もちろんバルタン星人は飯島監督が作り上げたキャラとして、それは広く認知されていて、バルタンといえば飯島監督、飯島監督といえばバルタンと、そう言われるまでに至っているが、その上で昨今のファンから見たときには、歴代作品で描かれた、バルタン星人というキャラや背景描写に統一性がなく、ウルトラの歴史の40年で描かれたシリーズを、一括した一つの流れとして捕らえたとき、設定を重視するファンの中からは、そこをして苦言を呈する人も少なくない。
しかし、その件について、筆者なりに弁護するのであれば、飯島監督にとって『ウルトラマン』におけるバルタン星人は、いつの時代でも、そこで「ウルトラマンの力を借りた人類が、未来に向かって乗り越えるための象徴」として描かれていたわけであり、それが例えば1966年当時の『ウルトラマン』であったときには、そこで宇宙へ旅立とうとする人類がもっとも大事にすべきポイントが、科学だった時代からこそ、そこでのバルタン星人は、互いに科学を用いながら拮抗するべき「侵略宇宙人」であっただけであり、それが35年を経過した『ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT』(2001年)においては、「異なる価値観を持ち合った他民族同士が調和するために、受け入れる心」だと、飯島監督の中で「人類が宇宙へ進む時に、改めて大切にしなければいけないこと」として、そのテーマが選ばれだけであって、なんら、そこにおいてはバルタン星人は「常に地球人にとっての、宇宙・未来へ向かうにあたって向き合うべき」対象としては、40年間、飯島監督にとっては、変化はしていないのである。