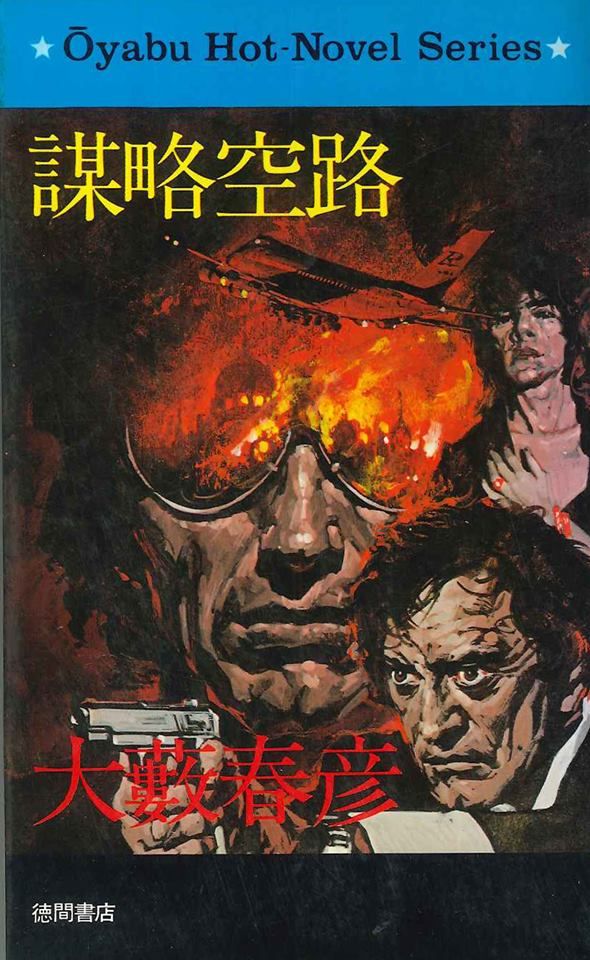さてさて。「小学校の頃の読書歴」に関する、強烈な思い出といえば、もう一方ではRoald Dahl『チョコレート工場の秘密(Charlie and the Chocolate Factory)』を挙げなければいけない。
話が出来過ぎのようでもあるが、筆者は大のTim Burton監督映画のファンである。彼の映画の中に漂う、寂しさをまとった「本当の幸福」は、宮沢賢治の「ほんたうのさいわひ」にも匹敵するだけの、リアリズムと説得力に溢れていると思っている。
だから、というわけではないのだ。
なぜならば、Tim Burton監督による映画化作品『チャーリーとチョコレート工場 (Charlie and the Chocolate Factory)』は、2005年の映画化作品で、筆者はその頃、そろそろ40歳を迎えようかという年齢であった。少年期の思い出を、ノスタルジィとマイノリティのTim監督が映像化してくれたことは、これ以上のご褒美はなかった。
あの頃、筆者は本当にこの『チョコレート工場の秘密』評論社発行の、田村隆一氏翻訳の児童用単行本に、どれだけのめり込んで、感化されたことか。
ここでも、寓話としての中核になるのは、資本主義の頂点に立ったように見えるワンカ社長(あえて田村翻訳版に敬意を表して「ウォンカ」ではなく)の工場は、資本主義的な意味での工場ではなく、インドのチョコレート城、クルミを剥くリスの群れ、白人社会では被差別対象になるであろうウンバルンバといった、多種多様なガジェットを盛り込むことで、地上のあらゆる差別や貧困、動物愛や人類愛といったファクターが、「チョコレートを生産する」という行為に置換凝縮された世界観であり、風刺文学としてもかなりの完成度を誇る。
作者のRoald Dahl氏は英国人だが、アフリカ滞在期間も長く(この辺りがウンバルンバに活かされていると思われる)、ブラック・ユーモアや風刺小説を得意とし、映画界でも『007は二度死ぬ』(1967年)『チキ・チキ・バン・バン』(1968年)の脚本も手掛けている。