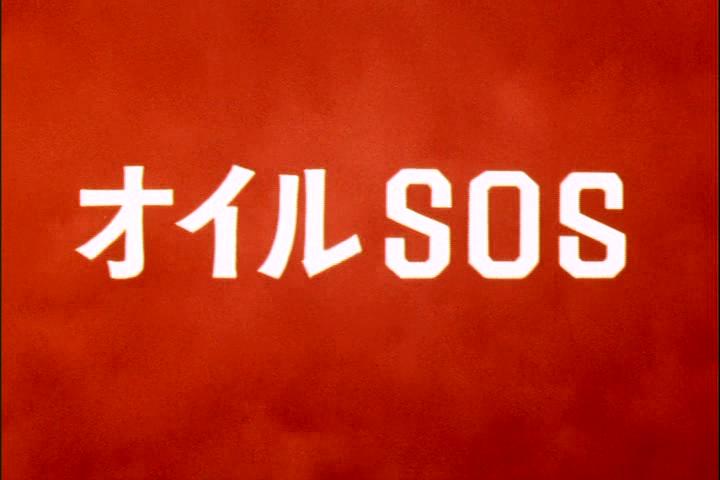これは例えるなら近年の邦画における、原田眞人監督の『突入せよ! あさま山荘事件』(2002年)や『クライマーズ・ハイ』(2008年)に近い、ドキュメンタリックな映画手法と似通っている。
そこには、役者の演技力に頼らない、綿密で緻密な演出計算が前提として要求され、コンテ段階での完成度が強く求められるが、むしろコンテの完成度を映像で表現しきれれば、完全にその映像世界は、作家の手によってコントロール可能なのである。
飯島監督の本話は、その強いスラップスティックギャグ性によって、視聴者にはそれと感じさせない作りにはなっているが、とてもドキュメンタリー性の強い全体構成によって成り立っているのである。
完全に余談になるが、本話で全編を包み込んでいた、そのギャグという表現はそもそも、今述べたような緻密な計算と、綿密な再現性によって生まれるというのも、60年代当時の娯楽の世界では常識であった。
上記した『ニッポン無責任時代』をはじめ、植木等やクレージーキャッツ映画を数多く撮って「古澤天皇」の異名を欲しいままにした古澤憲吾監督は、まだ演技的には素人だった植木等氏を使って、ギャグコメディを描くにあたって、「ここで何秒かけて振り向いて、何秒かけて煙草をくわえ、何回吸って何回吐く」というようなコンテを綿密に切って、秒単位コマ単位で植木氏に演じさせたという。
また、昭和バラエティの金字塔の『8時だョ!全員集合』(1969年~1985年)もまた、毎週のコントを製作するに当たっては、当時のプロデューサー・居作昌果氏や、ザ・ドリフターズの面々が、毎週数十時間もの時間を使って、綿密に構成を練っていた。
飯島監督の作品というと、牧歌的な雰囲気、生き生きとした子役俳優、軽妙な掛け合いのギャグなどがすぐ思い起こされて、それらは時として軽妙さとともに軽んじられてしまう傾向があるが、「何も考えずに楽しめる娯楽」が「何も考えずに作られているわけはない」のと一緒で、軽妙でアクティヴな演出が目立つ完成作品において、飯島監督の演技指導は、他のどの監督よりも厳しく、子役にすら妥協を許さなかったという。
それは、飯島監督がなによりもコンテの大切さを知っていて、画面設計を大事にしてスタジオに挑んでいた証拠なのであろう。
スタジオに入るまでに、コンテ段階で精密機械レベルの構築を行い、生身の役者とスタジオを前にしたときに、どれだけそれを再現させられるかに腐心していた飯島監督だからこそ、その時その時の作品のジャンルや方向性が、どれだけふり幅があっても、それに対応して、一定のクオリティの作品を送り出せていたという結論がそこに在る。
飯島監督という演出家は、決して気分やセンスに頼るだけの作家ではなかった。
映像作品を観るときに必要なのは、その映像作家の作家性への洞察はもちろんであるが、もっと大事なポイントは、その作家性が果たして、どのような映像理論や映像力学で、実際の作品へと落とし込まれていっているかの検証ではないだろうか。
いずれ検証することもあるとは思うが、飯島監督が実相寺監督にとって、生涯一番の親友であったことの根底に流れていたのは、「職人・飯島と、芸術家・実相寺」などといった表層的な見え方の繋がりなどではなく、実は共に、映像理論の基本を頑なに守り、その上でフィルムに「個」を刻み込んだ、同時代の戦友であったからではないかと、筆者は推測している。
ウルトラは、様々な形での戦友同士を生み出してきたが、上原正三氏と市川森一氏、その市川氏と山際監督のように、作家性では真逆に見える部分を見せ合いつつも、その根底に流れていたのは、常に、互いへのリスペクトとライバル心と、テレビドラマ制作という戦火を潜り抜けた、共通の記憶なのかもしれない。