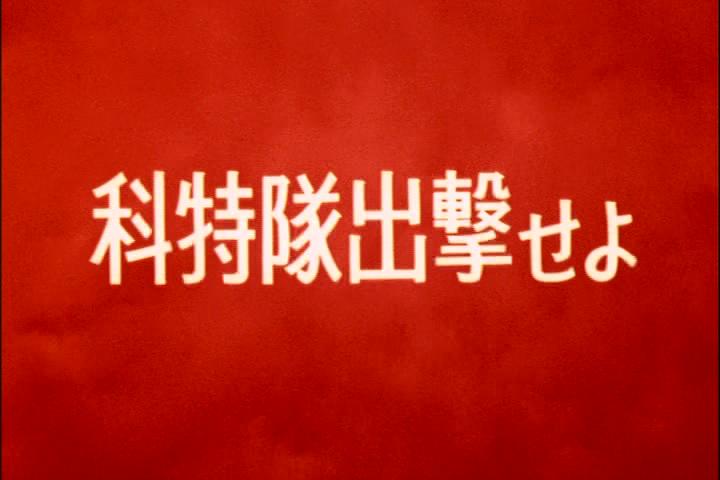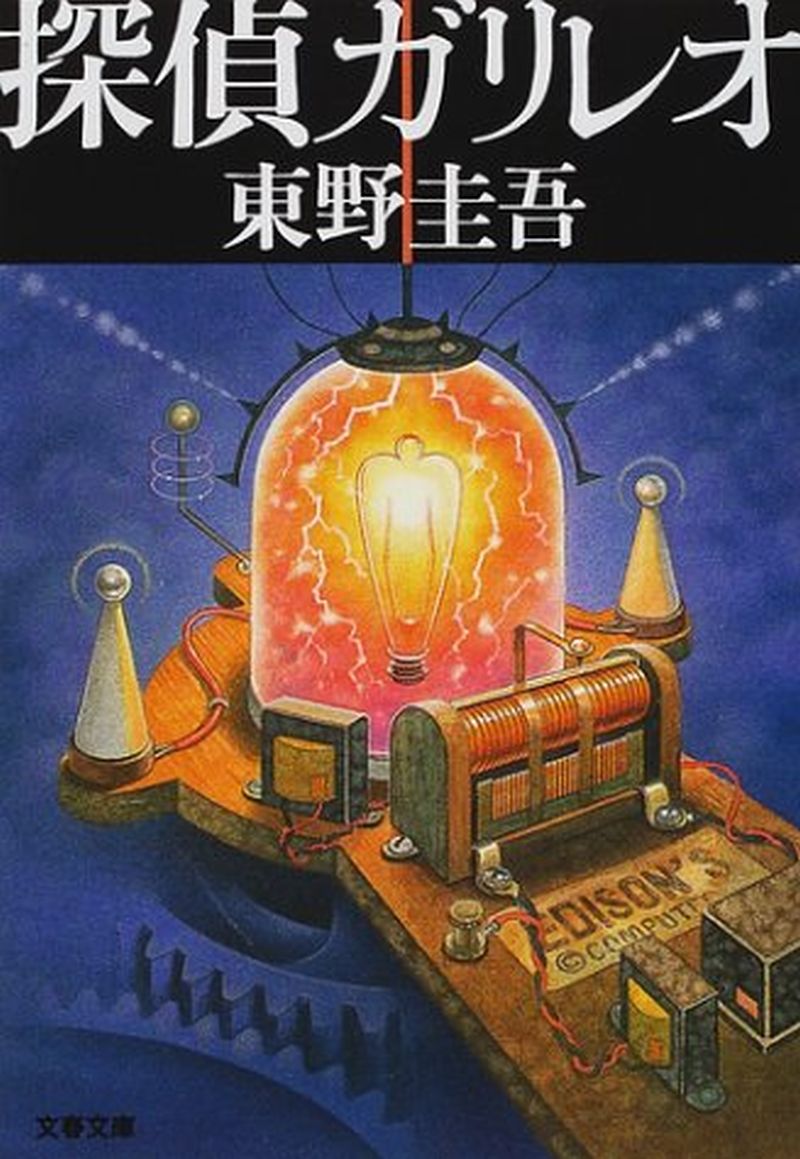「生々しさ」への信心
今回かなりの尺を割いて記したが、この富野メモが書かれた1978年は、ヤマトブーム、SFブームの渦中であると同時に、『宇宙戦艦ヤマト』『ベルサイユのばら』等の大ヒットにより、アニメの過剰なロマン傾倒、大時代的なドラマ主義、その上での、宝塚的な感情的、感傷的、起伏の激しい芝居のありようが、「思春期向けのアニメ演出の王道」とされていた時代でもある。
『宇宙戦艦ヤマト』でも『サイボーグ009』でも『ベルサイユのばら』でも、主人公たちはまるで旅芝居一座か劇団四季の、舞台の上の役者のように、大声を張り上げて己の心情を哲学的に、または直球で叫び、頭を抱えて涙を流し、嗚咽して愛を求める台詞をまた叫ぶ。
“そういう演出”が“これぞドラマだ”と思いこまれていた。
その歴史的事実と比較すると、上記した富野メモの、恐ろしいまでの冷徹な「現実を見る目」「生々しさへの信心」が手に取るように分かる。その一説は、「ヤマト」という単語を用いなくても、『ガンボーイ』背景設定の解説に端的に表れている。
なぜ敵に異星人を使わないか。(昨日までは異星人であった)
キネマ旬報社『ガンダムの現場から』『ガンボーイ』企画書より
①異星人共存は、一方の破壊で終わる。→力おしの話だけで、救いない。(自由への論理が一方的になる)
一方の論理のドラマはドラマではない。
②今回のテーマに対して不満。
①の理由により
〇戦いの原因が、宿命的因縁によらねばならない限り、人間的ドラマとならない。
〇人間的ドラマにしなければ、自由は語れない。
まして愛さえも。
〇のりこえるべきもの、かち取るべきもの、のドラマに、感動をよびおこすのは、べきものの原因の中に、共通の“種”が造り出す(生み出す)障害があればこそ、べきもの、への対立、抗争が、ドラマとしての感動を呼ぶわけだ。
これは明確に『ヤマト』を仮想敵としたアジテーションだろう。
『ヤマト』は明確に、敵を(欧米的白人種をディフォルメした)異星人であるとした上で、その異星人を「倒すべき悪」と決めつけ、正義の味方側は皆、宇宙時代なのに日本人で、漢字の名前を持ち、旧日本軍の大艦巨砲主義の象徴の戦艦をそのまま宇宙に飛ばして、正義と愛を謡いながら八面六臂の大活躍をさせてティーンズを熱狂させた。
つまり、『ヤマト』はSFのラベルは借りているが、完全に、前時代的太平洋戦争日本帝国軍賛美の、破壊と排除と「正義とはこうあるべき」「愛とはこうであるべき」「これがロマンだ」を、大声でがなり立てるしか能がないアニメであったからである。
上記した部分を含め、富野監督がこの時点で、「ヤマトブーム」「大ロマン大芝居主義(いずれ書くが、富野監督の自伝『だから僕は…』を読む限りにおいては、ここでの仮想敵にはおそらく、当時アニメファンの間で「長浜ロマンアニメ」と持てはやされていた、『超電磁マシーン ボルテスV』(1977年)『闘将ダイモス』(1978年)等の、長浜忠夫監督作品も含まれていたのかもしれない)」をつぶそうと思ったとき、つぶさねばならないと決心したとき、何をカウンターとして、自らの信心の発露を提示するのかを、自覚していたことが読み取れる。
「テレビで一番俗悪だと思われている“ロボット物”を使って『ヤマト』をつぶす」とは、つまり、人の普遍的なドラマ、人の生理に訴えかける演出や、生の人間らしい作劇を積み重ねることで、「虚構でしかない“ドラマモドキの三文芝居”の跋扈を打ち破る」ことでもあったのだと言えよう。
それは、アニメだけではなく映画、テレビドラマの世界でも同じ現象が起きていて、しかしその中において、富野監督とは関係なく、実写畑で一つの才能と現象が生まれつつあった。