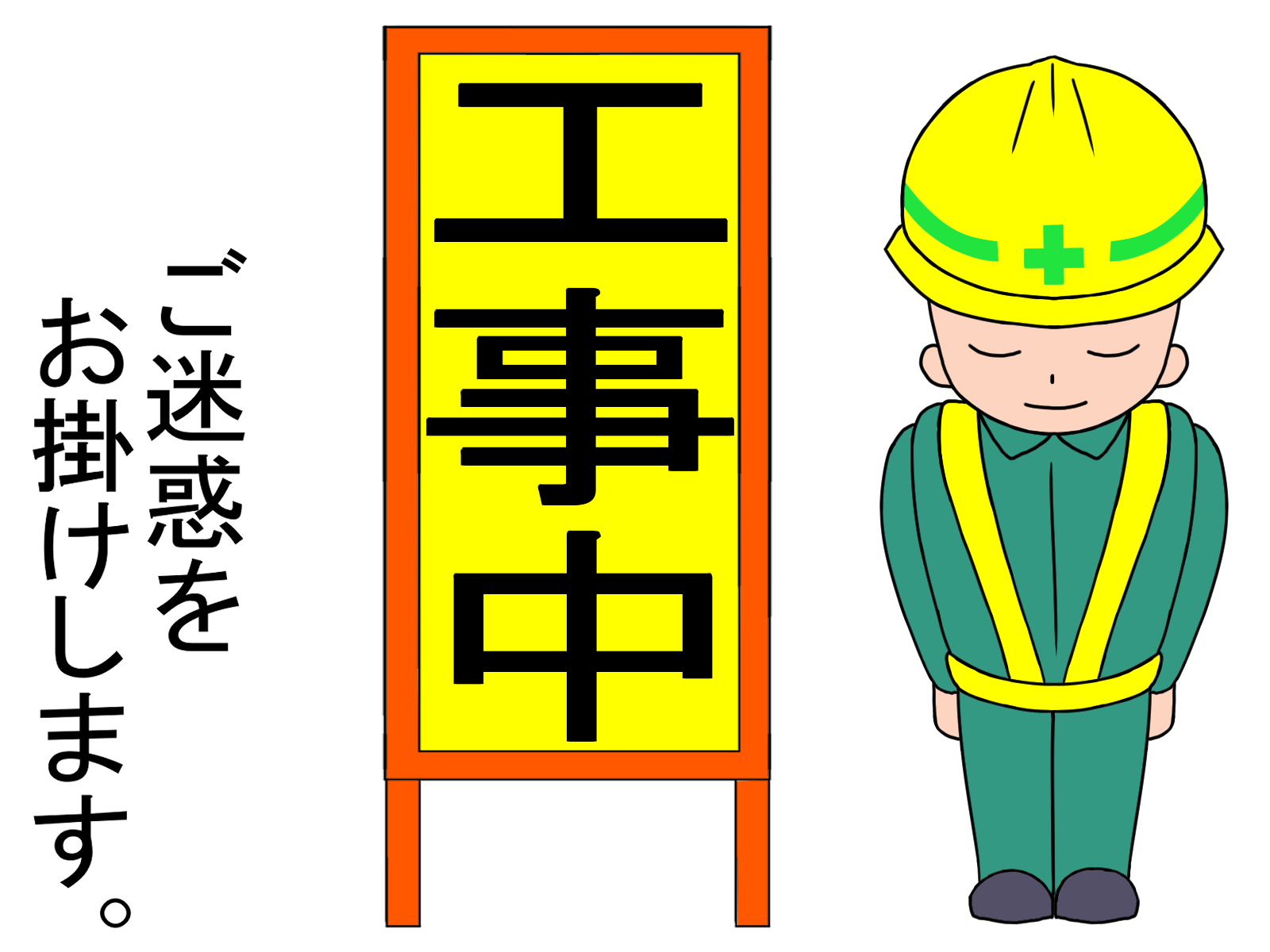やがて菅野昭彦脚本『消された時間』によって、宇宙人セブンと地球人との一体感が揺さぶられ、若槻文三脚本『ダーク・ゾーン』によって正義の概念が破棄され、自ら書いたはずの『狙われた街』さえもが、最後の最後に加えられた、佐々木守氏の筆によるナレーション一つで、コスモポリタニズムを成り立たせているはずの信頼関係まで崩されて、金城氏は、まずどれから対応してアンサー脚本を書けばいいのか、八方塞になってのではあるまいか。
そこで金城氏がまずアンサーすべきと選んだのは、実はセブンのどの脚本でもなく、前作ウルトラマンの『故郷は地球』であったのではなかろうか?
それはおかしいとの指摘も受けよう。
しかも、評論家諸氏の評論にもあるように、既に『故郷は地球』へのアンサー脚本は『小さな英雄』で書かれたと言われている。
しかし、しかしである。
かような疑問の全てを受け止めてもなお、本話『ウルトラ警備隊西へ』が持つ、その正統派娯楽編の影に隠れた、ささやかな違和感にすっきりした回答を見つけるには、『故郷は地球』という作品の存在を借りなければ、説明が出来ないのだ。
その違和感の全ては、後編でのダンとドロシー(の姿をしたペダン星人)との会話のシーンに集約されている。
ここでドロシーが述べる地球糾弾論は正論だ。
それは一見、この前後から頻出する、「侵略側にも一部の理あり」に通ずる正義の相対化にも見える。
地球人には地球人の正義があり、宇宙人には宇宙人の正義があり、それは時に相容れないものとして、対立としての戦争を生むという、後にアニメ作品等で頻繁に見ることになる構図が描かれている。
しかし、その後の展開はそういったテーマを内包していない。
ペダン星人のその正論は、あくまで侵略を行うための詭弁でしかなく、しょせん宇宙人は侵略者であり極悪でさるゆえに、セブンとウルトラ警備隊によって、容赦なく殲滅されるという展開がその後に描かれるのである。