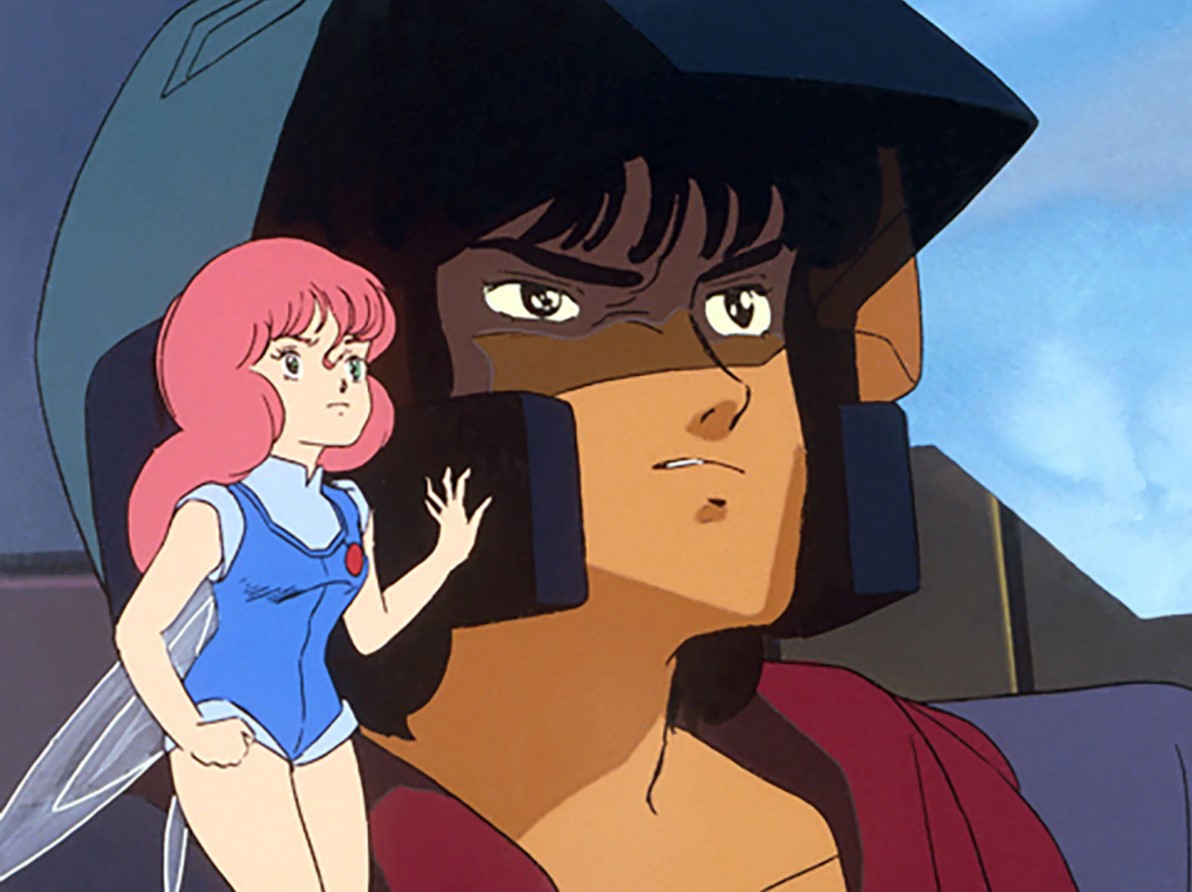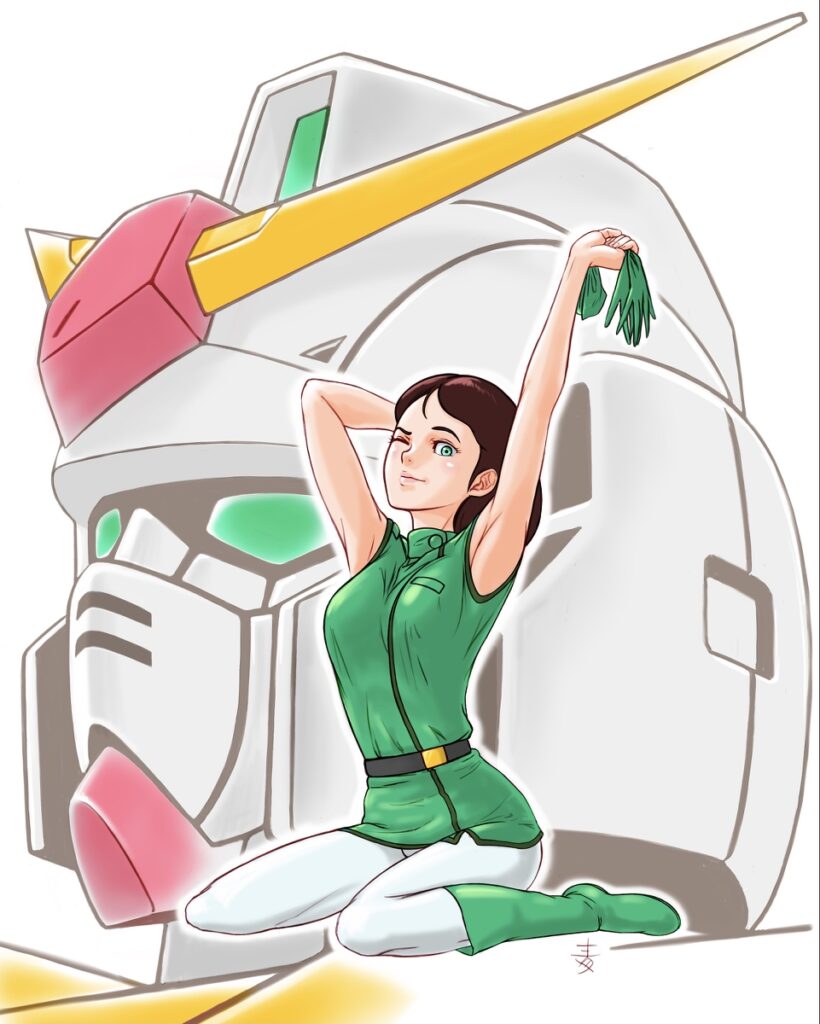前回は『佐々木守論「『アイアンキング(1972年)』が戦った時代【前編】』

本作『アイアンキング』(1972年)を知る多くのマニアは、ここまで書いてきたような要素や特色が、前面に強く打ち出された佐々木守作劇の初期の不知火一族編を高く評価する側面が強いが、実はじっくり観ていくと『アイアンキング』のテーマ性や「面白さの真骨頂」はむしろ、シリーズが後半へ向けて進行して加速していくにしたがって、味わい深さも増していくのである。
『不知火一族編』では、毎回登場するゲスト女優は、あくまで弦太郎・五郎コンビとは、密接な繋がりを持てずに、ドラマ世界から去っていく役回りが多かった。

それは、そもそも当初はメインヒロインに高村ゆき子という存在が据えられていたからでもあり、そこではまだ弦太郎は人間でありながら、人間として当たり前の感情や心情を知らない人間として登場していたからである。
しかし第10話『死者へのくちづけ』でゆき子の死をきっかけにした弦太郎の成長と変化は、確実に「何かのスイッチ」が入れられて、この独立幻野党編では特に毎回登場する女性と、なんらかの形で心情的に深く関わり、そこでの女性達は皆聖女か母のようにイノセンスに、弦太郎に「人としての大切な何か」を与え教え、託して消えていくようになるのである。
そして弦太郎は、そこで目覚めるたびに、そこでの「イノセンスな聖女」達に「戦争が起きている現実」を、教えなければならない役目を担うのだ。
例えば、独立幻野党編初期の第12話『東京非常事態宣言』第13話『地下要塞攻撃命令』の前後編。
ここで独立幻野党の一人卯月(演ずるは『帰ってきたウルトラマン』(1971年)でMATレギュラー・上野隊員だった三井恒氏)の恋人である怜子(夏純子)に「貴方は本当は寂しい人なのよ」と言われた時だけ、弦太郎は(シリーズ中で初めて女性キャラを)「さん付け」で呼んだ。しかしその、怜子の言葉すらも、弦太郎を油断させて隙を作ろうとする独立幻野党が怜子に言わせた甘言でしかなかったのだ。それはあまりにも無垢な「純愛」の心がなせる残酷さ。弦太郎はそれを見抜くことが出来ず、敵の罠にはまる。
そこで描かれる怜子の心情は、卯月への想いゆえであり、感情が欠落した弦太郎には、それを見抜くことは出来ずに危機に陥る。怜子は恋人の卯月のことしか見えない。そして独立幻野党の国際会議テロは進行する。卯月は革命の崇高さと組織への忠誠心だけを唱え、怜子の懇願を拒否し、独立幻野党幹部は「弦太郎を殺すか。卯月と共に組織に入るか」と」怜子にけしかける。
その次の瞬間に「怜子、本当はお前の事が好きなんだ」と卯月に言わせる展開は、ここが天才・佐々木守の筆ならではの巧みさでもあるのだが、再び顔を合わせた怜子と弦太郎は、心を許しあうかのように見えて「互いが互いの殉ずるもののために、互いを信じてはならなかった現実」を思い知る。
それでも弦太郎は「理解できない中で必死に」怜子を救おうと、怜子が卯月と共に独立幻野党へ向かうように優しく声を掛ける。そして戦う。弦太郎は戦うことでしか「生きる術」を知らないからだ。その死闘の中で、怜子の口から独立幻野党の隠れ家の場所を知った弦太郎は、怪獣ロボットをアイアンキングに任せて、敵の隠れ家に乗り込み卯月をも殺す。
弦太郎はラストに怜子に「君を思ってるふりをした……すまん」と言い「どうしても奴らの本拠地を聞き出したかったんだ」と語ったが、「騙されていることは最初から分かっていたのに!」と泣き叫ぶ怜子に刺される。
弦太郎と怜子は、互いに命に代えても殉じたい存在の為に偽りの言葉を交わしあったのだ。「これでいいんだ……」痛む傷口から血を流す弦太郎の台詞でこの話は終了するが、「それでいい」のは、実は弦太郎の方だけである現実が、後味のほろ苦さを誘う。
本当は弦太郎は、怜子を騙してなどはいなかったのかもしれないのだから。
その胸中は、視聴者にも、五郎にも、もちろん怜子にも知らされずに物語は幕を閉じる。