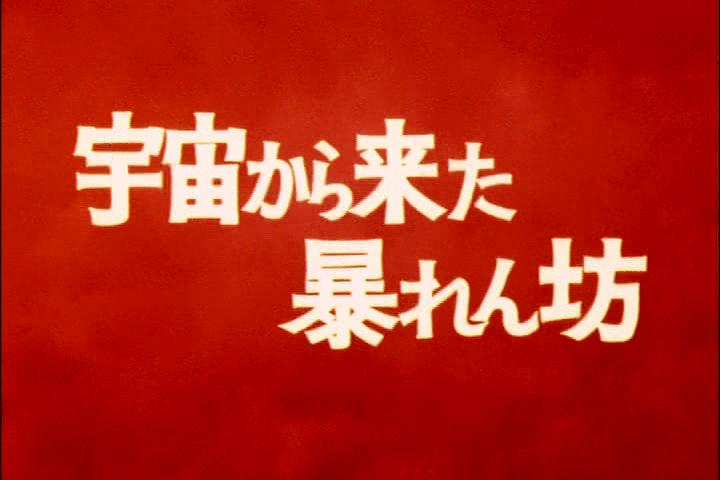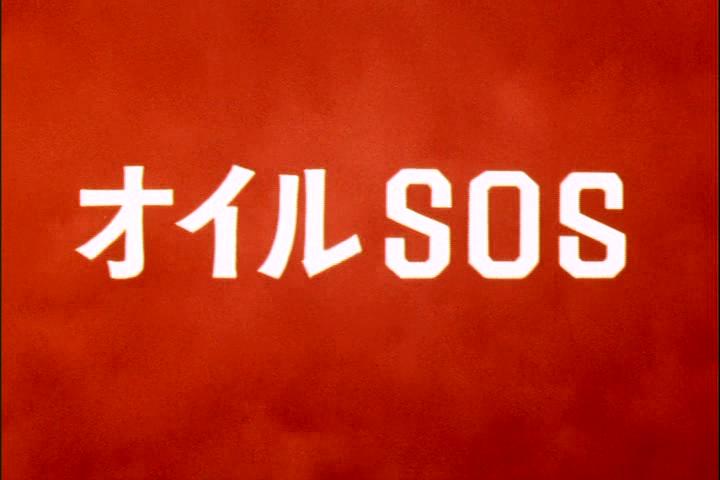これがもし、実相寺氏がコンティニュティや繋がりさえも、アクロバティックに構成する作家であったなら、映像理論や力学に知恵を持たないタイプの、ほとんどのウルトラファンや視聴者、子どもは、そこで繰り広げられている映像に対して、芸術派とも前衛的とも思う隙すらないまま、「何がなんだかよくわからない」と認識するしかないはずなのである。
「コンテは教科書レベルの基礎・基本を守り、非凡さや個性を構図やアングルで発揮する」
このやり方は、ある意味では、第二期ウルトラにおいて映像派監督として知られた、真船禎監督がやはり得意としていた手法である。
また、全く逆のやり方である「アングルや構図はとても安定した描写だが、モンタージュ・コンティニュティの独特さで、他にはない特性の作品を生み出す」という点では、安藤達己監督、山際永三監督の作品が、これに当たる演出を行っている。
一応映像理論では、アングルや構図は視覚へ影響を与えて、コンティニュティ、モンタージュなどの要素は、視聴者が感じる時間軸への影響を与えるという基本理念がある。
安藤監督の『あなたはだぁれ?』での、小林昭二氏の主観で流れる浮遊感のある時間や、山際監督の『3億年超獣出現!』での、久里虫太郎と超獣ガランの同調だけが有する(ウルトラマンエースとの戦闘とは隔離された)時間の流れ方などは、これらはコンティニュティがもたらした要素であり、実相寺作品においては、そういった「時間の流れる感覚が独特」という作品は、ATG映画『曼荼羅』(1971年)『哥』(1972年)などを見渡しても、実はそれほど多くはない。
そもそも映像というのは、カメラとフィルムを使うことによる「現実の切り取り」が基本である。
現実にカメラを向けているだけでは写せない、夢を紡ぐ特撮やアニメであっても、突き詰めた言い方をしてしまえば「特撮セット」や「フレーム台の上のセル画」という現実を、カメラで切り取ってフィルムに焼き付けているのである。
逆を言えば、それがドラマの1シーンで、住宅街のロケ地で俳優を写すのだとしても、ドキュメント映画の取材対象であったとしても、それは特撮セットでミニチュア相手に暴れる、ゴムとウレタンの着ぐるみ怪獣と等価である。
大事なのは、どういうコンテと、どういった画面設計と、どのような色彩・照明設計で、そこ(流れるフィルム)に「世界」を構築して、自分の主観をフィルム上に定着させていくかである。
映像作家の仕事とは、そのようにして自らが紡ぎあげた映像世界を、視聴者に疑似体験させるのが、役目であり役割なのだ。要は、自らが作り上げた、映像の画面構成とモンタージュで構築された閉鎖世界へと、どうやって視聴者・観客を引きずりこむのか。そこがポイントなのである。
それを、映像作家個人が個人の感性でやってのけるのが映像。
しかし、映像は決して個人作品という側面だけで成立しているのではなく、そこでは様々なプロフェッショナルや作家が集まって現場を成立しているのであって、そういった現場を統括するのもまた、監督の仕事なのである。
数十人、数百人単位のスタッフをまとめて、その数百の想像力の中に共通のビジョンを植え込み、自分が思い描く完成映像へと結実させていく過程では、現実的な対応や譲歩が求められる。
それを実相寺監督に当てはめるのであれば、実相寺氏の発信目的はあくまで、そこでの一瞬のカッティングの中の、画面構成や構図へ向けられていたわけであり、逆にそれ以外の要因、特にそこで語られるドラマのテーマや方向性や、それを語るべきコンティニュティやモンタージュに関しては、氏はとことん無関心だったのである。