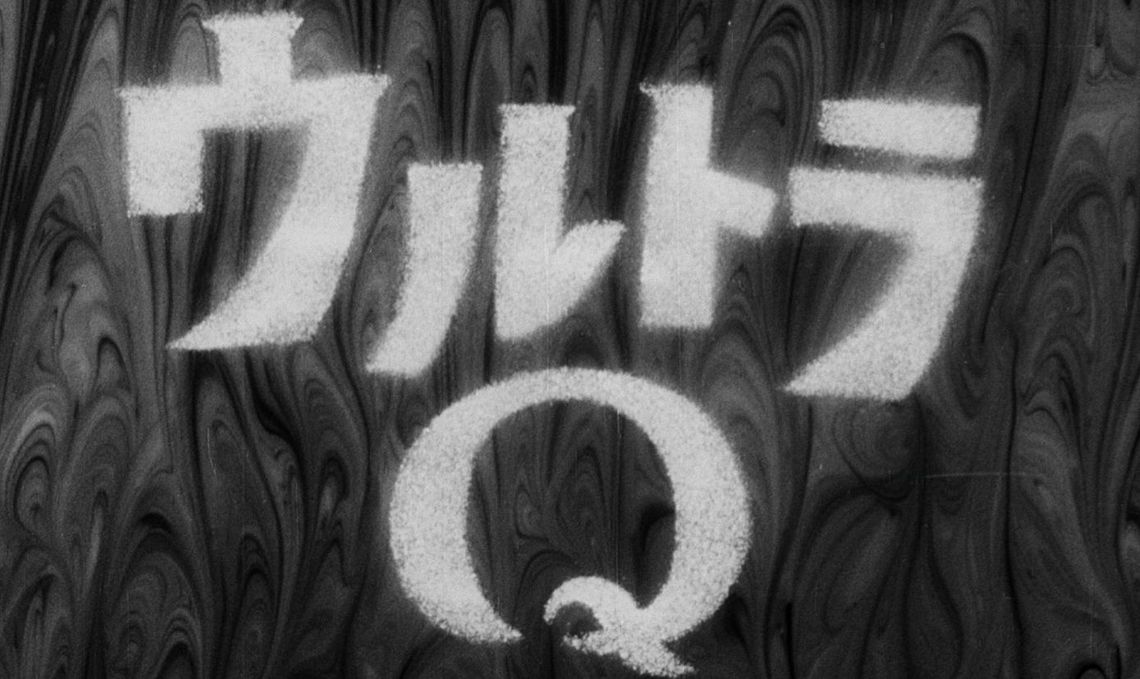ジャミラ・清二・吉野・太郎・菊。
佐々木氏は、どの心情とも決して同調することなく、彼らと彼らを取り巻く環境の描写に勤め、ドラマという混沌がはじき出す化学反応の結果のように、ラストシーンまでを描き続けたのである。
「日本という国家が体裁と秩序を保つ為に、排除していった者達の行く末」は、佐々木作品に常に流れていたテーマだった。
それは『日本春歌考』(1967年)等の、大島渚監督作品の脚本についても同等であり、『男どアホウ甲子園』のような、野球漫画でも普遍のテーマだった。
筆者やあなた方が今生きられているのは、誰のおかげで、どんな犠牲の上に成り立っていたのか。
それを知らないという罪こそが、最大の悲劇なのだということを、佐々木守氏は常に問いかけていたのだ。
ならば我々は何を尊び、何を大切にすればよかったのだろう。
フィクションの世界で、そして現実で起きた悲喜劇は、どうすれば避けられたのだろうか。
その答えはきっと、70年代という時代を駆け抜けた、佐々木守作品の全てに散りばめられていたのだろう。
今回の文章では、最後に『故郷は地球 佐々木守シナリオ集』に書かれた、佐々木守本人による、後書きの一説を書き写しておきたい。
偉大なる先人の魂を胸に……。
「大江健三郎氏は、文化勲章を辞退するに当たって、確か『戦後民主主義者の自分には国家からの勲章は似合わない』といった意味の談話を発表された。
僕にはその『戦後民主主義者』という言葉が嬉しかった。
思えば十年前。
大和書房から出版して頂いたシナリオ集『ウルトラマン 怪獣聖書』の後書きで、僕は心の底に、あの石川県の片田舎の小学校で教えられた『戦後民主主義』が生き続けていると書いている。
僕にとっての戦後民主主義とは、教室から教壇が無くなったことであり、先生の位置がその教卓と共に、教室の一番後ろに移ったことであり、そしてグループ授業がはじまり、勉強はそれぞれのグループで自由に進めて、わからないところだけ先生に訊くという方法であり、それまで口をきくことも憚っていた男と女が、手を取り合って、フォークダンスを踊るということであった。
あの『戦後民主主義』が五十年間着実に歩み続けていれば、イジメやそれによる自殺といった悲劇は、絶対に起こるはずがなかったと僕は思う。
『戦後民主主義』は、いつ、なぜ崩壊してしまったのであろうか」
『故郷は地球 佐々木守シナリオ集』