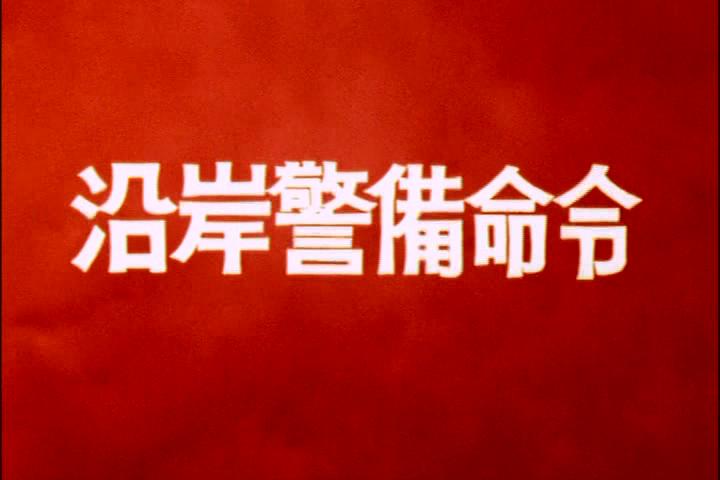なかなか酷評ばかりになっていてしまっている、筆者の平成ウルトラ評であるが、この、飯島監督の劇場版1作目と、他作家による平成ウルトラ劇場版との比較評論に関しては、またこのサイトで『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』(2006年)の評論でしっかりと行いたいと思う。
詳細はそこで書き込んでいく予定なので重複は避けるが、結論だけ先に書いてしまえば、平成ウルトラのスタッフの多くは「ウルトラマンが存在するのだ」という夢の尊さをアジテーションしながらも、決して、それを貫き通すためには何をするべきかを子どもに提示することがないということ。
それは、平成ウルトラの数多くを手がけた、小中和哉・長谷川圭一コンビの『ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦』(1999年)『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』などに非常に顕著に現れている。
そこでは頻繁に「信じることが勇気」などという綺麗な台詞が羅列されているが、そこで登場した主役の子どもが、ではウルトラマンを信じるために何をしたかというと、ただ、流されるままに状況に翻弄されながら「何でも願いが叶う球に願いを言う」「目の前で戦っているウルトラマンを応援する」だけという展開しか用意されていない。
もちろん、小中・長谷川コンビはそこで決して「夢を信じ続けることの難しさ」の、正体としての現実を描くことはなく、結果として上記した2本の映画作品はどちらも「ウルトラマンを信じてさえいれば、あとは何もしなくても大丈夫」レベルの掘り下げで終わってしまっているのだ。
そこの危うさ、脆弱性などは、改めてメビウス劇場版の評論で述べたいと思うが、逆にこの『ウルトラマン コスモス THE FIRST CONTACT』で唸らされるのは、同じように「ウルトラマンが存在するんだと信じた少年」の夢と希望が「目標や夢を貫き通し続けるためには何が必要なのか」「そういった『目の前の現実』を乗り越えるだけの価値を、自分の夢に持たせられるか」「自分の想像力の枠を超えた現実が、自分の夢を阻もうとするのが社会なのだ」などといった要素と、しっかりとセットでバランスよく配置されて描かれているということだろう。
それがどんなファンタジーであっても、描こうとする要素の綺麗な面しか描かないというのは、これは送り手として不遜であるし、子どもへ作品を送る大人としては卑怯である。
高度な童話・寓話・ファンタジーは(というか、むしろそもそもそれらは)そこでは必ず「想像の果てにある創造」が、「生臭い現実」とワンセットで同居するのだ。
むしろ、後者の存在を忘れたり無視したりしてしまえば、それらの非現実的要素は、途端に意義も意味も失ってしまう。
しかし、そこで「大人が子どもへ」という構図でその発信が行われるときには、そこでのスタンスや切り口、描き方などにおいて「そこでの作り手の大人が、何をもってして『子どもに見せるべき現実』や、『子どもからの批判を覚悟の上で、提示しなければいけない現状』をストラクチュアするか」そこが明確に現れてしまうのである。
筆者の目から見たときには、『ウルトラマンティガ』以降の平成ウルトラには、姑息な大人の目線が感じられるのだ。
小中・長谷川コンビに限らず、平成ウルトラではどこかで、作り手たる脚本家・監督達がまず率先して、現実から逃げている印象が感じ取れる。
平成ウルトラが連呼した「ウルトラマンがいると思ってもいいんだ。信じることが勇気なんだ」は、子どもへの責任ある大人からのメッセージではなく、作り手が、自分たちに自己暗示をかけるように言い聞かせている図にも見える。
その証拠に、平成ウルトラでは(この『ウルトラマン コスモス THE FIRST CONTACT』劇場版他の一部を除いて)「では、本当にウルトラマンがいなかったときには(というかウルトラマンなんて現実にはいない)それを全肯定してそそのかした平成ウルトラの作り手達は、大人としてどう責任を取るのか」について、なんら具体的なエクスキューズも用意されていない。
飯島監督の本作は、そのことへの警鐘に満ちている。
アニメ作品においての、宮崎駿監督作品『未来少年コナン』(1978年)や富野由悠季監督の『戦闘メカ ザブングル』(1982年)安彦良和監督の『巨神ゴーグ』(1984年)などで描かれた核がそうであったように、夢や希望を持った思春期までの青少年がすべきことは、考える前にまず、動くこと、行動すること、突き進むことである。
小賢しい知恵などはまずそこでは不要であり、生き抜き夢をかなえる為に必要な洞察力や観察力や経験則は、机上でいくら本やネットと向き合っても手に入らない。机の前に座って夢想しているだけでは手遅れになるだけである。
とにかく動けば何かにぶち当たる。ぶち当たった物は必ず「現実」である。
人は、ぶち当たった現実の数だけ経験を得る。
むしろ、それ以外で「夢を叶えるだけの力」を手に入れることは出来ない。
ぶっちゃけて言えば『新世紀 エヴァンゲリオン』(1995年)前後から台頭し始め、『涼宮ハルヒの憂鬱』(2006年)辺りの萌え系作品に至るまでに顕著な「なんでもかんでも受動的な主人公が、状況周辺でウロウロしているだけで、優柔不断でしかない言動が、過大な結果を招き寄せて成立する物語」が伝えているのは、「何もやる気がない、動く勇気もない、動いて失敗するのが怖い、傷つくのが怖い」そんな今のオタクユーザーに、すり寄ることで銭をせしめようとする狡猾な送り手か、その危うさにも気づけない「目くそ鼻くそ」レベルの送り手の所業である。
批判を承知であえて言い切るが、人生において何かを得るためには、自らが動かなければ決して結果はそこには発生しないし、自分が動いた結果、ぶち当たる壁は(自分がどう思おうが願おうが)「変わらない現実」である。
そこで百歩譲って「現実を受け入れなくても、現実から逃げてもいいんだよ。都合の良い夢想だけ信じているのも、それはそれでアリなんだよ」が、オタク社会という、閉じた市場で納得済みの需要と供給システムの中で成立することに、我々大人が異論を挟まないのだとしても、そもそも、自我形成期前後の幼児・児童が観るウルトラにおいて、作り手がそれをやってしまうというのは、これは既に第二期ウルトラにおける「教育」よりも罪深く「やばい」ことなのではないかと、筆者などは思うのである。