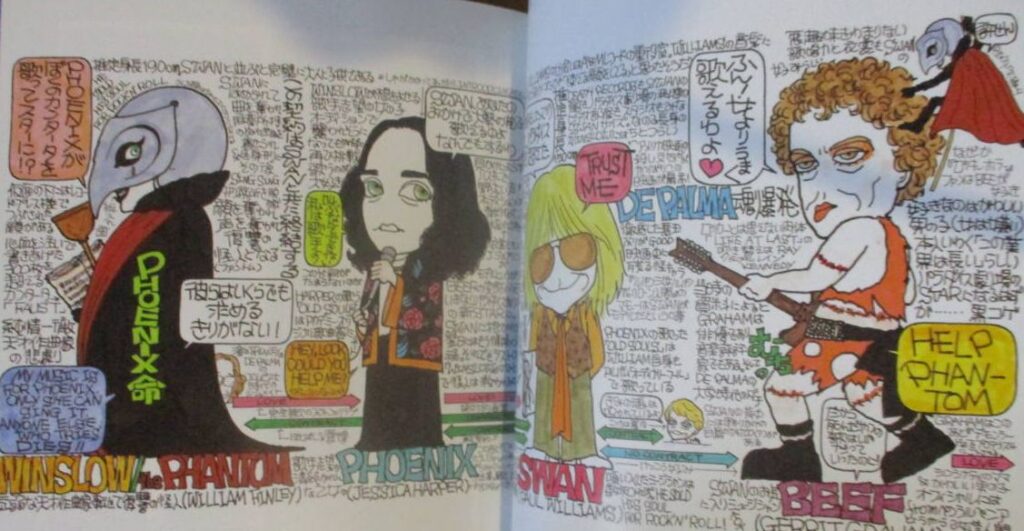一応、実相寺監督の著書『星の林に月の船』『夜毎の円盤』『ウルトラマンができるまで』『ウルトラマンの東京』などを読めば、実相寺監督本人によるアナウンスによって、当時の心境を窺い知ることは可能ではある。
けども、それが果たして、本当に当時の本心を語っていたかというと、そうとは限らないから、人というのは面白いのではないだろうか。
例えば、若い頃、特撮ヒーロー役者としてデビューしたにもかかわらず、その作品を恥じてしまい、一時期俳優としての活動履歴から抹消するが、後年、それを撤回してファン活動に勤しんでくれる俳優さんは少なくはない。
下世話な物言いをしてしまえば、若い頃は演出家も俳優も、「ジャリバンに関わった経歴」はあまりプラスに働かないからだ。
社会や業界で評価が高い仕事ではないのに、そこで演じたヒーローや演出のイメージがいつまでもこびりつくことで、後の仕事に悪い影響が出ることもある。
今では「仮面ライダーは僕の青春でした」と語り、仮面ライダー道まで説いてしまう藤岡弘氏だって、実は『仮面ライダー』(1971年)当時は、人気役者になってまで変身物を演じるのが嫌になり、NHK大河ドラマへの出演を巡ってトラブルになり、結果いきなり失踪して、撮影に穴を開けてしまう大問題を起こしていた。
そういった意識問題は、顔出しが命の役者だけにあるわけでもない。
筆者は20代前半のころ、とある劇団と関わっていたことがあり、ある日自分はその劇団の演出家先生の専用室の棚になぜか『ミラーマン』(1971年)のビデオを見つけてしまったことがある。
「なんでミラーマンがここに?」と演出家先生に質問してみると「昔監督をしたことがあったんだよ。
あの頃は仕事なんか選べなかった。ジャリバンなんてやりたくなかった。でもやるしかなかった。反省の意味も含めてそこに置いてあるのさ」という返答が返ってきて、業界で仕事をしながらも特撮ファンでもあった自分は、笑顔を返しながらも心の中が寂しかった思い出がある。
ではなぜ、そこまで毛嫌いしていた「ジャリバン仕事」を、後年になっていきなり快く受け入れるようになり、ファンサービスまでするようになる俳優・演出家が多いのか。
個々に理由は違うのだろうし、様々な要素が組み合っていると思うが、ひとつには、役者として演出家として、若い頃に自分の目指した本来の方向性への結果が、人生という時間のスパンの中で、ある程度出尽くした後の晩年であれば、それまで封印したかった過去仕事などへの心の余裕も生まれてくるだろうし、数十年を経てそれを愛してくれるファンの存在を知ったとき、自分の過去の仕事の価値そのものを、見直すようになるのもまた人間だろう。
また、下世話な分析をしてしまえば、華々しくヒーローを演じたりして脚光を浴びた後、そこから様々な作品や役柄に挑戦することでヒーロー脱却を図ったけれども、結果として役者としては大成しなかった役者さんというのは少なくなく、そういった人達が現代のオタク文化の流れの中で、当時を振り返り、美化し、ファンにおもねる著書を発行するだけで、それなりの経済的な見返りを手に出来るという現実もあるのかもしれない。