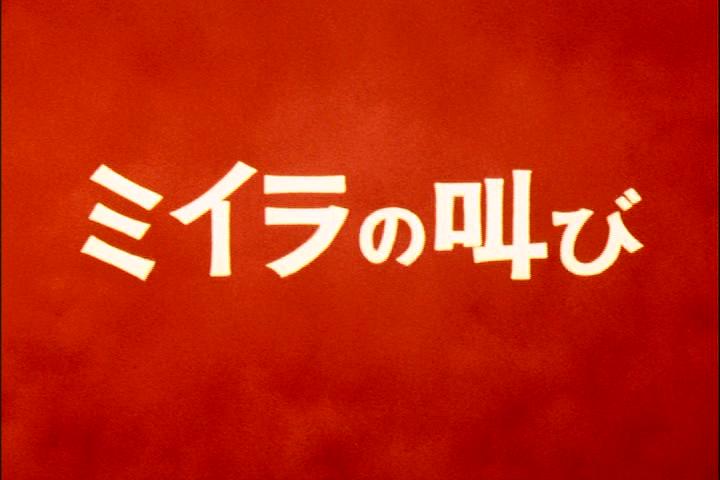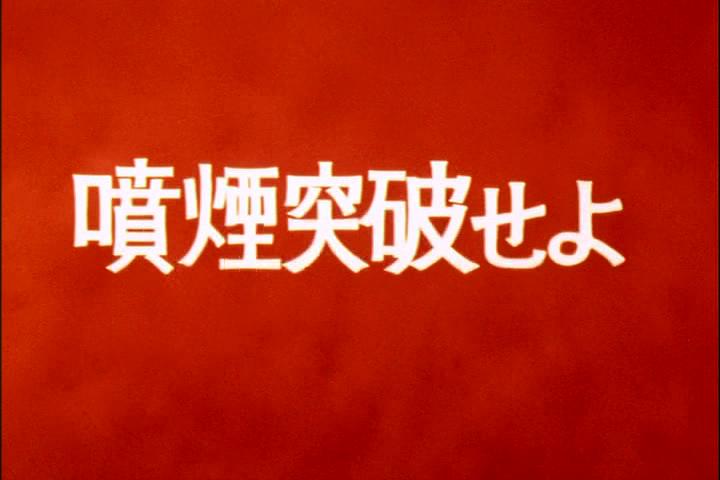本話は、脚本に佐々木守氏の名前が冠されているが、実際は監督をした、実相寺昭雄氏が脚本も手がけたことは、ウルトラファンには有名である。この話はドラマ的にそこから実相寺イズムを読み取ろうとすると「完全に侵略者の兵器として扱われる怪獣」「光と闇のコントラストとロジック」そういった要素を読み取ることが出来るのだが、しかし、やはり映像作家であった実相寺氏が全てを作った作品だけに、そこでは文芸的なテーマ優先のドラマ作りではなく、まず撮りたい映像かくありきの姿勢を、窺い知ることが出来るのである。
「前衛芸術映画作家」「映像派の鬼才」「光と闇の魔術師」様々な異名で評され、特にウルトラファンからはもてはやされた実相寺監督だが、今回は、この実相寺監督が果たしてそこまで評されるほど異端な映像作家だったのか? 実相寺監督ご本人は、自身の作風や撮り方が普通だと嘯いていたと伝えられているが、それは単なる、シャイなポーズだったのか?その辺を検証していきたいと思う。
まず、結論かくありきで言い切ってしまうと、実相寺監督が異端の映像作家であるという、歴代のウルトラファンがリスペクトとして語るその肩書きには、筆者は首を傾げざるをえない。
その根拠はこの後いろいろな形で検証していくが、実は実相寺監督は、あくまで「個性的な画面構成を作る作家」であっただけで、実相寺映像作品を構成しているその他の要素を俯瞰して解析すれば、むしろご本人が自ら語っていたように「普通の映像作家」であったわけで、妙なロジックになるが、映像理論や映像力学に対して素人の方々が「これは特殊だ」と、そう感じるという要素こそが、実相寺監督が「実は変ではなかった」なによりの証拠なのだ。
映像を構築するために、映像作家が学んでおかねばならないことは無限に多いが、そこでの基本というのは、以下の各種にまとめられる。
・構図、アングル、奥行きなどを含めた画面設計
・カットの繋ぎ方、モンタージュ
・照明設計
・色彩設計
これら映像理論の構成要素は、全て有機的に絡み合って一つの作品を生み出す要因であり、そしてこれらの要素は全て等価である。だから、もしも実相寺監督が前衛芸術派であり、全ての映像技法において前衛的手法を有していたタイプの作家であって、そこで作られた映像作品に前衛表現的な思惟が込められるのであれば、それぞれの要素全てに(必ずしも均等・均一ではなくても)、前衛的な要素が含まれているのが普通であるし、また自然である。
さて、そこでウルトラファンによって、実相寺監督に対して貼られた「映像派・実相寺」「前衛芸術映像作家・実相寺」というレッテルに戻って考えてみると、そこで主にレッテルの原因として語られるのは「実相寺アングル」が殆どである。
後述するが、実相寺監督は、そのアングルや画面設計に関しては確かに独特であり、いや、むしろそこのみを切り取られて「映像派」と呼ばれている意味合いが大きい。
逆を言えば、実は既存のウルトラ系評論において、実相寺氏のコンティニュティや、モンタージュの個性に対して言及した評論や評価は殆ど見られず、では、それはなぜかといえば簡単で「実は実相寺氏のコンテやモンタージュは、殆どはそれは、基本どおりの常識的・教科書的なコンテであり、そのカットの繋ぎ方、流れに関しては、なんら前衛的でも芸術的でもない」からである。
しかしそれは決して、実相寺氏が凡庸な映像作家であったことを意味する要素ではない。
むしろ逆である。
実相寺監督は、そのアングルや構図の取り方こそが野心的であったわけであるが、むしろその奔放なアングルや構図は、基礎どおりのモンタージュやコンテがあってこそ、成立を許された自由さであるのだ。