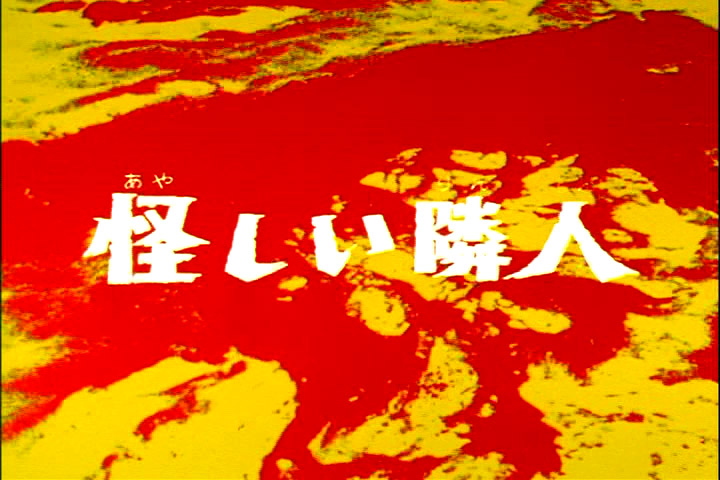閑話休題。
右田脚本に対する違和感はまだまだある。
物語序盤、少女姿のピット星人は、ソーラー大博士の家に深夜忍び込み、ソーラー大博士をわざわざ眠らせて、目の前のパソコンからウルトラ警備隊のデータベースにハッキングし、怪獣エレキングのデータを抹消させるが、『湖のひみつ』と本作では、エレキング自体の属性や特徴が、電気怪獣から地球温暖化炭酸ガス怪獣(笑)に変化しているのだから、1967年時のデータがあってもなくても、まったく問題はない。
脚本のケアレスミスはまだある。エレキング初登場時、ウルトラ警備隊のエレキングデータが抹消されていたため、フルハシ隊長は自分の記憶で、エレキングの背景にいるのはピット星人だとウルトラホーク1号のコックピットで悟ったが、それは地上にいる他の隊員には伝わっていない筈なのに、エレキングが去ったすぐ後の会話で隊員が「じゃあピット星人はそれを知ってて……」と口にしている。
もっと矛盾があるのが、ダン少年が、ピット星人の女性から、エレキングも円盤もピット星人もエネルギーが太陽だと告げられるシーン。ここはひょっとすると「みんなエネルギーは太陽なの」という台詞を使いたかっただけかもしれないが、文脈的にはそれでは、万能素敵未来夢満載の太陽エネルギーが、炭酸ガスと熱を発する怪獣のエネルギー源になってしまうのだが、通産省的にそれはいいのか?という問題になってくる。まさかと思うが、なんでもかんでも太陽エネルギーが未来宇宙科学最先端モードでありさえすれば、運用や適用に関してはいっさい拘らないというイデオロギーであるはずもなかろうに。「みんなの太陽を悪いことにつかおうとするから罰が当たったんだ!」これのどこが、エンディングの「まるでうまくまとめました」的な「太陽の厳しさ」なのだろうか?
そして、上でも書いたが「あれから四半世紀、セブンが何をしていたのか」が説明される、第17支部格納庫での「横たわり眠るセブンと、それを見つめるフルハシ」のシーン。
正直、本当に子どもの頃から『ウルトラセブン』というヒーローも番組も好きだった人にとって、ここで倒れて眠るままのセブンと、それを見つめて泣きながら「大馬鹿野郎だ」と悪態をつくフルハシ隊長のシーンを見て、落涙しないファンはいないのではないだろうか。
それぐらいに名シーンであるし、毒蝮三太夫氏の名演技も光り、このシーンがあるだけで、この作品は観る価値があると言い切っても過言ではない。
それだけに「あれから、いくつの戦いに挑んできたのだろうか」という追加ナレーションを、巧いと受け止めるか「分かってない無粋さ」と受け止めるかで、またこのシーンの評価は変わってくるだろう。
あの、ゴース星人撃退の夜が明けてから数日、地球に落下したまま昏睡状態のセブンがひっそり回収されて、そのまま四半世紀倉庫で眠っていた、それを今知っているのはフルハシだけだった。そっちの方が、多分(少なくとも筆者は)感動が増したと思う。瀕死だったセブンが宇宙へ戻ってから数十年元気に戦ってきた謎のひみつには、「ソーラーパネルをイメージさせるセブンは、常にいつでも元気に働いてくれていなければいけない」通産省的な都合でもあったのだろうかと邪推はしておくが。
それにつけても、物語が後半、攻めてくるエレキングと、眠ったままのセブン、拉致されたダン少年、という形で分断されるが、それらのパートの分離と融合は、中々演出が上手く噛み合って物語が進行していくのではあるが、逆にテンポよくそうして物語が展開し続けると、今度は物語中盤から一気に出番が減ったアンヌの存在価値が、急速に失われて行ってしまうのである。
例えば、第17支部格納庫にセブンが収容された連絡が入ったタイミングで、アンヌもフルハシと共に急行していて、そこでセブンと再会していたら、なんらかの作劇やモノローグや、セブンへの語り掛けで、アンヌの四半世紀の心情を救い取ることも可能だったのだ。ここでアンヌとセブンを再会させるハコであるなら「セブンはずっと宇宙で戦い続けて行方不明だった」からの、アンヌの人生の選択も肯定されるしレスキューできる。
しかし、右田脚本は、中盤以降完全にアンヌを置き去りにした。
クライマックス、蘇ったセブンは、ここは往年のファンには嬉しいところだが、森次氏の声で掛け声だけではなく、等身大になってダン少年を助けて円盤に乗り込み会話もしてみせる。
しかし、全てがハッピーエンドで終わるラスト。決してモロボシ・ダンには姿を変えず、巨大なウルトラセブンのまま、ウルトラ警備隊一同や謎のソーラー大博士一家を見下ろして、無言で通じ合う……はずのシーン。
筆者の穿ちすぎかもしれないが、そのシーンでは、どうにもアンヌが手持無沙汰で、名台詞の一つがあるわけでもなく、居心地が悪く見えてしまうのだ。いや「それ」は決してひし美ゆり子氏のせいではない。脚本や演出が、そこでアンヌは何を思い何を伝えたいのかを、ほぼ用意していないのだ。最愛の状態で死に別れに近い形で見送った人が今目の前にいて、生きていたことが分かって、自分の今の最愛の息子の命をも救ってくれて、その存在をも肯定してくれて。
そこでアンヌが言うべきこと、ひし美ゆり子氏が演ずべきことは膨大にあっただろうに、右田脚本も神澤演出も、特にそこになんの重心も置かないまま、非常に淡白にシーンを終えてしまうのだ。
「現代のファンを相手にウルトラをやるんだから、四半世紀前の恋愛とか要らないでしょう」では済まないのだ。
それが「要らない」のであれば、フルハシの「大馬鹿野郎だ」の涙も「要らない」はずになってしまう。
つまり、このラストシーンから逆算してしまうと、「要らない」のはフルハシの言葉でもダン少年でもなく「アンヌの存在」になってしまい、そういう意味ではこの作品は、最終的な因数分解の段階では、ひし美ゆり子氏に対して、大変失礼な脚本と演出が、当初から用意されていたというしかないのである。
……とまぁ、ここまでは、右田脚本の「なんでそうなっちゃうの?」だが、ここからは特撮マニア的な「思い入れの空振り」や、神澤監督のドラマパート含む演出の問題点を挙げていきたいと思う。
まず、特撮オタク的な難癖から付け始めてしまうと、肝心の主役。コンテンツの看板たるウルトラセブンの着ぐるみが、そもそもアトラクション用の改造という時点でもういろんな意味でガッカリなのだが、まぁ素材はショー用でも、実際に撮影する際にブラッシュアップさせることはいくらでもできたはずである。
実際、元から装備されていたのかどうかはともかく、ビームランプと目の機電は機能しているし、アイスラッガーも脱着可能になっている。
しかし、なんというか、歴史を一方通行で眺める時、セブンファンがずっとがっかりしていたこと。「本編終了時からセブンのプロテクター凹部が金色」がそのままなのである。最初に放映された『ウルトラセブン』で、主役のセブンのプロテクター凹部はクリームホワイト。それが、直後の『怪奇大作戦』(1968年)『ジャガーの眼は赤い』に出てきた「ウルトラセブンのサンドイッチマン」が、既にプロテクター凹部が金色に塗られていた。公式映像ではこれが初だっただろう。

それ自体は悪い事ではない。俳優でも、映像でのメイクと舞台のメイクは全く異なるやり方が用いられるのと同じだ。
しかし、それを映像で使おうというのであれば、特撮の現場関係者の誰かが映像を一つでも見れば気付く違いなのだ。我々放映当時からのセブンファンは「金色プロテクターのセブン」と「黄色い目のウルトラマン」に、どれだけ期待を裏切られてきたか。円谷プロサイドは90年代中盤になっても気づいていないことの証だった。
造形面で言えば、初代のセブンの背中の両肩肩甲骨部分にあった電池ボックスの膨らみも消えていて、イマドキのオタク的拘りの「細部とディテールが全て」ではないが、順序論から言って「そこ」まで気配りが行き届いていない仕事には、正当な続編は名乗って欲しくはないという気持ちは正直強い。
細部やディテール、という意味では、ウルトラセブンが本編後の客演やショー、グラビア等、いわゆる露出の公で、上西弘次氏アクションを再現しようとした最初のセブンであることの意義は大きい。
『ウルトラセブン』『ウルトラ警備隊西へ』評論でも書いたが、上西氏は剣道の達人であったので、構え方が自然に剣道で刀を両手で握った構えになる。こうしたスーツアクターの癖や独特のポーズを、後の作品でも再現しようという発想は円谷プロには長年なく(東映は、70年代から大野剣友会などが率先して徹底していた)、ちょうどこの時期、オタク俳優でもある京本政樹氏が、雑誌の企画で円谷のウルトラマンや東映の仮面ライダーを再現したり、アドバイスして回っていて、『ウルトラマンG』の段階で、「ウルトラマンにはウルトラマンの、ウルトラセブンにはウルトラセブンの、構え方や蹴り方や物腰などが個々にあるんだ」を提唱して回っていたという。
そういう意味では、まずウルトラマンにおいて、「古谷敏の構えと動きを意識して映像に登場した初代ウルトラマン」は、この作品の前年に東映との共同で制作されたVシネ『ウルトラマンVS仮面ライダー』(1993年 監督・雨宮慶太)が先鞭をつけた。
本作の上西調セブンと、Vシネの古谷調ウルトラマン。どちらも試みは評価するが、2020年代の今の完コピが当たり前になった視点で見ると、ジャンプした時の足の延ばし方や、攻撃を避ける時の物腰など、細部の詰めが甘い。まだまだこの時期の制作サイドは「セブンは脇を締めて両手をぐっと握っておけばいい」「ウルトラマンは腰を落として、両手をふわっと構えればいい」程度の認識で停まっている。