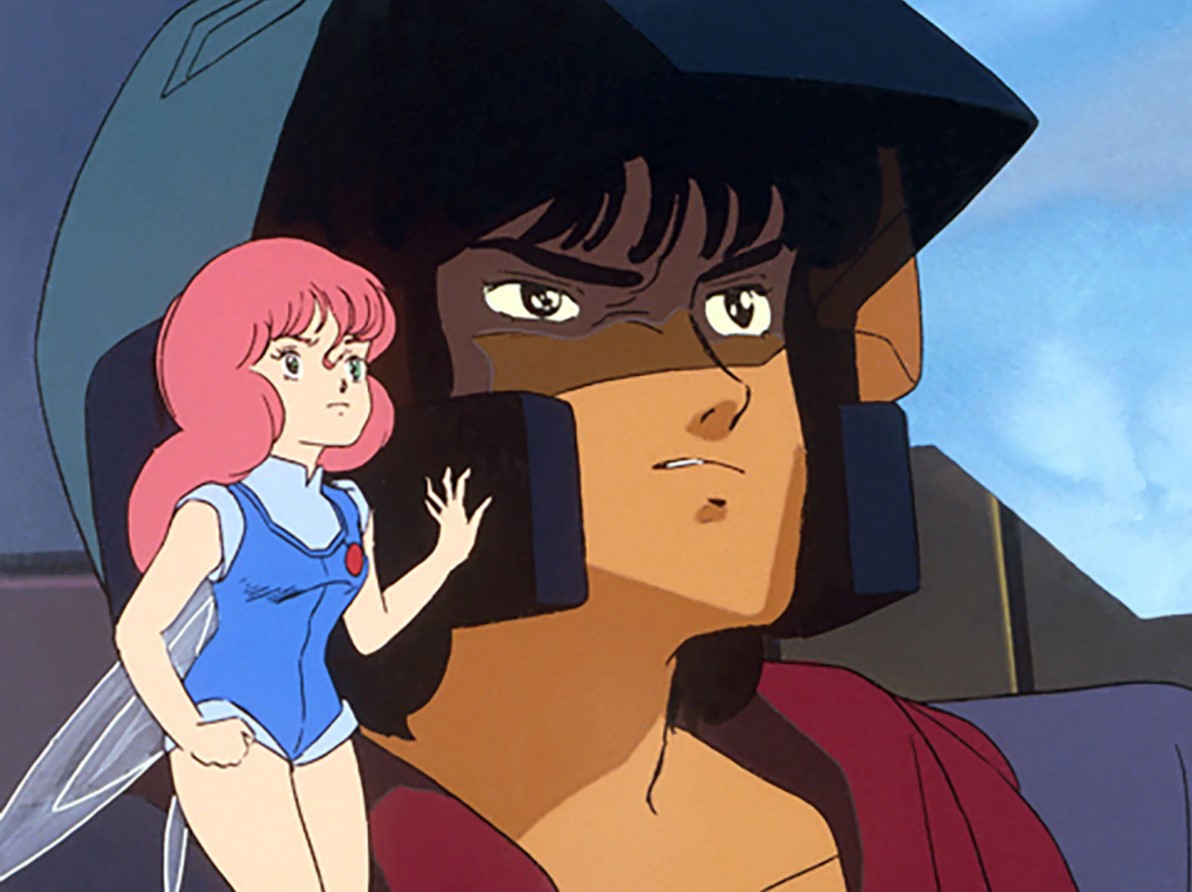その後のパートにも、細かい矛盾があちこちに飛び火してしまっている。
青い光球でやってきた怪獣・ヤナカーギー(嫌な(やな)+顔(カーギー)=ヤナカーギー)と、赤い光球で現れた初代ウルトラマン。そして舞台が竜ヶ森湖という設定は、そこでの円谷英二氏の出会いや出くわした事件が、『ウルトラマン』第一話の『ウルトラ作戦第一号』に繋がるというロジックは極めて明確なのだが、余計なお遊びや、省かれた流れなどが、その疑似メタ構造に不要なフィルターをかけさせてしまっている。
そもそも、ヤナカーギーのデザインと造形は、ベムラーに似せる必要は、それはテーマ的に必然だったのかもしれないが、そのベムラーを当時改造した着ぐるみの、本作の演出家の担当回の別怪獣の方にむしろ寄せて似せる必要など、そもそもあったのだろうか?という素朴な疑問。あと、ヤナカーギーの登場シーンが基本的に夜間シーンばかりなので目立たないが、どうやら腹部には、オレンジで「円谷」と漢字で模様が描いてあるという趣味の悪いお遊び感。これらには、あまりシンパシィを感じて肩入れできないのも正直な本音である。
脚本上でのミスなのか、演出の「ノリノリ過ぎ」なのか判断に困るシーンは他にもある。
そもそも、「怪獣を買いに来た」という目的で登場したはずのチャリジャが、なぜクライマックスに竜ヶ森湖に向かって「ヤナカーギーよ。チャリジャが迎えにきたぞ」と叫んで、冒頭と主旨が変わるのか。文脈的には、最初に登場した際に「生き別れた相棒怪獣を見つけたい」や「ウルトラマンに封印された相棒怪獣を助けにやってきた」でなければ話が繋がらなくなるのである。
そして今一歩かっちり手応えが収まらないのが、ヤナカーギーとティガの戦いが、露払いなのは良いとしても、そこで初代ウルトラマンを生んだのは「円谷監督の想い」なのか「金城哲夫の努力」なのか、あやふやな演出なまま、円谷監督の「ヒーローが必要なんだよ、金城くん」という名台詞が、どういう流れでその後、金城氏に伝わり『ウルトラ作戦第一号』の脚本に結実したのかが丸々欠落している呆気なさ。
というか、この流れでは、ティガは露払いどころか、少なくとも円谷英二にはヒーローとしては認知されていない扱いになってしまうのだが、それは脚本家と監督的には良いのか、プロダクションや出資者的には良いのかという問題も残る。実際、ラストシーンで主人公は「あのウルトラの星はどうしたんだろう? 僕も、もっともっと力が欲しい」とモノローグで語っているが、それはとりもなおさず、現役主人公をウルトラマンとして否定してしてしまっていることに繋がらないだろうか?
「ティガのいる世界」で、怪獣が現れティガが現れ戦う図は、その世界の住民にはお馴染みの図かもしれないが、ティガが全く認知されていない「1965年の円谷プロの近く」では、怪獣相手にティガが戦っても、ウルトラマンとしてはともかく、そこに居合わせた円谷監督は、ティガをヒーローとしても認知していない。これは文芸の上原氏による現行ウルトラへのアンサーなのか。それとも演出家による、自分のノスタルジィ至上主義の産物なのか。
苦言はまだある。はぐれてしまったヤナカーギーという相棒怪獣がいるのに、なぜチャリジャは登場冒頭では怪獣を欲しがったのか。「ヤナカーギーをトップとする怪獣軍団の兵揃え」が目的だったのか。それとも「メタ的に『本当の怪獣』がいない」を、怪獣番組でいきなりアナウンスしてしまおうとしたのだろうか。
また、ヤナカーギーとウルトラマンの関係の「なんとなく」も、「赤い宝石、ウルトラの星の意味と存在意義」も、「撮りたい絵柄優先」で撮って繋いでいってしまう「30年変わらぬ、監督に向いてない適正」によってボヤケてしまって、今一歩終始座り心地の悪い椅子で鑑賞させられた気分になる。
主人公と「円谷プロの助監督」の、長野博氏の一人二役のお遊び辺りは心底どうでもよく、メタとフィクションファンタジーの境界線が、悪い意味で混沌になってしまっている。
上原節を読み解こうとしても、各所にちりばめられていて、しかも映像力学的に「間違っている」監督個人の思い入れが邪魔をするようにちらかっていて、結果的に30分物として仕上がっているのが本作なのだ。
筆者は『ウルトラマンティガ』には入れ込んで観ている身ではなかったので(いずれ別項で解説)、主人公とチャリジャの光線の撃ち合いの軽さや、ヤナカーギーの肩に乗ったチャリジャの合成が酷い等は、これは「ティガに肩入れして観なかった当初からの理由」の一つでもあるので、ここで文句は言うまい。
しかし、「本当の怪獣を探す宇宙人とタイムリープ」「『ウルトラQ』制作時代の円谷プロへのタイムスリップ」「そこで描かれる、人間・金城哲夫と円谷一」「ウルトラマンと友情を結ぶ、円谷英二」「後の『ウルトラマン』第一話を予見させるクライマックスの展開」と、良質でメタファーフィクションとして「夢を育むプロダクション」の黎明期と、そこで苦闘していた金城氏を描いたという事は、先行していた『星の林に月の舟』『私が愛したウルトラセブン』には、決して負ける素材ではなかった。
結果として演出家による公私混同と、半世紀経っても進歩しない映像技術論によって、物語の核心部分がぼやけてしまった感は否めないが、「ウルトラマンのシリーズの一話の中で、ウルトラマンを産んだ、金城哲夫、円谷一、円谷英二を描く」という試みは、他の二人の先行作があればこそ、意義のある作品になったことは事実であろう。
「ヒーローが必要なんだよ、金城くん。ヒーローが必要なんだ。ヒーローが……」という言葉を、架空の世界の円谷英二氏に言わせた意味。ヒーローとは英雄であり、戦う闘士である前提であったと考える時、やはりここでも『帰ってきたウルトラマン』(1971年)後半での、市川森一氏とのイデオロギーバトルの再燃とその結実を見た気にさせられる。市川氏が書いた『私が愛したウルトラセブン』でセブンは「彷徨える魂」そのものの象徴であった。しかし、上原ヒーローは「義を重んじて戦い抜く闘士」ヒーローの定義である。
本作中の円谷英二は、ヤナカーギーに苦戦してピンチになるティガをして、ヒーローとは呼ばなかったし、なんの反応もしなかった。懐のウルトラの石が飛び、真なるウルトラマンに姿を変えて、一撃でヤナカーギーを葬ったウルトラマンを仰ぎ見て「ヒーロー」と初めて言い切った。
上原正三版「ヒーロー」は、優しさと屈強な闘争心が根底にあって、それは『光の国から愛をこめて』『帰ってきたウルトラマン』論でメインに述べているが、「人を苦しませ悲しませ、踏み躙った存在を、決して許さない心」それがヒーローであり、そういった意味では上原ウルトラマンは金城ウルトラマンとも市川ウルトラマンとも佐々木ウルトラマンとも違っているのである。
本作も、『セブン』や『星の林に月の船』とは違って、逆にウルトラマンティガの一話を借りた姿であるからこそ、ノスタルジィへの甘えは一切ない。それは本来のシリーズの主役であるティガが、全く劇中でヒーローとして扱われず、しかも全編を終えて現代へ戻ってきた主人公へ、上原氏曰くティガは本来の意味でのヒーローではないと断罪したことになる。