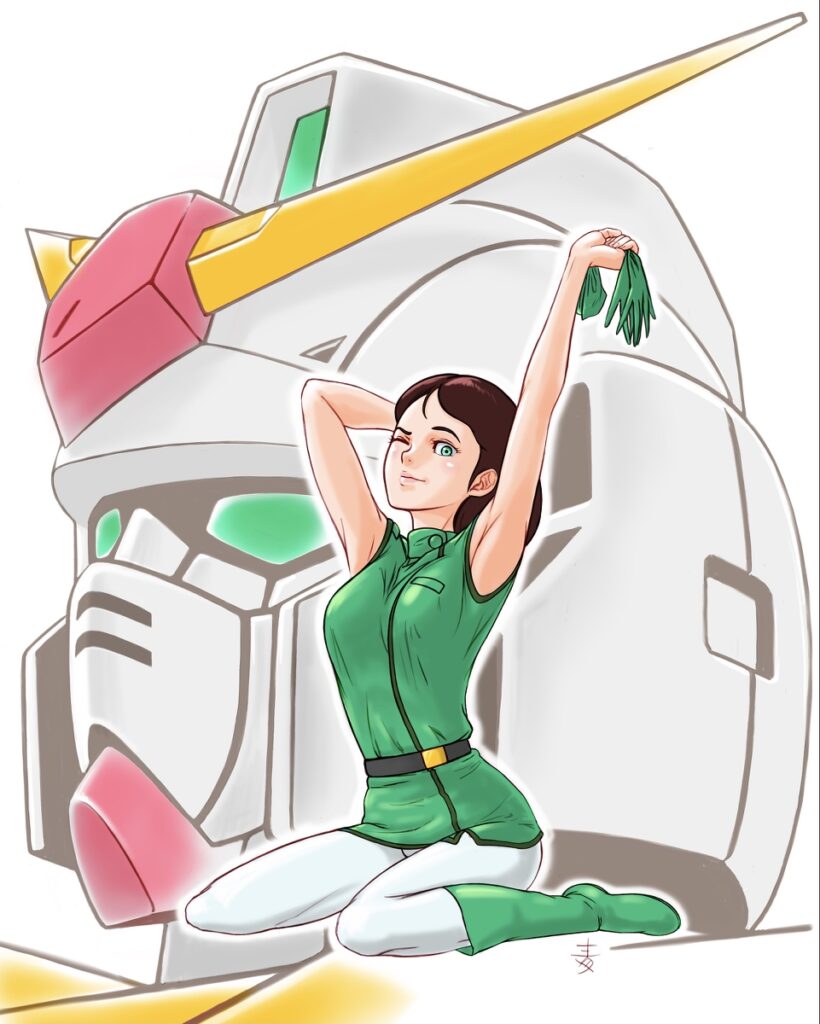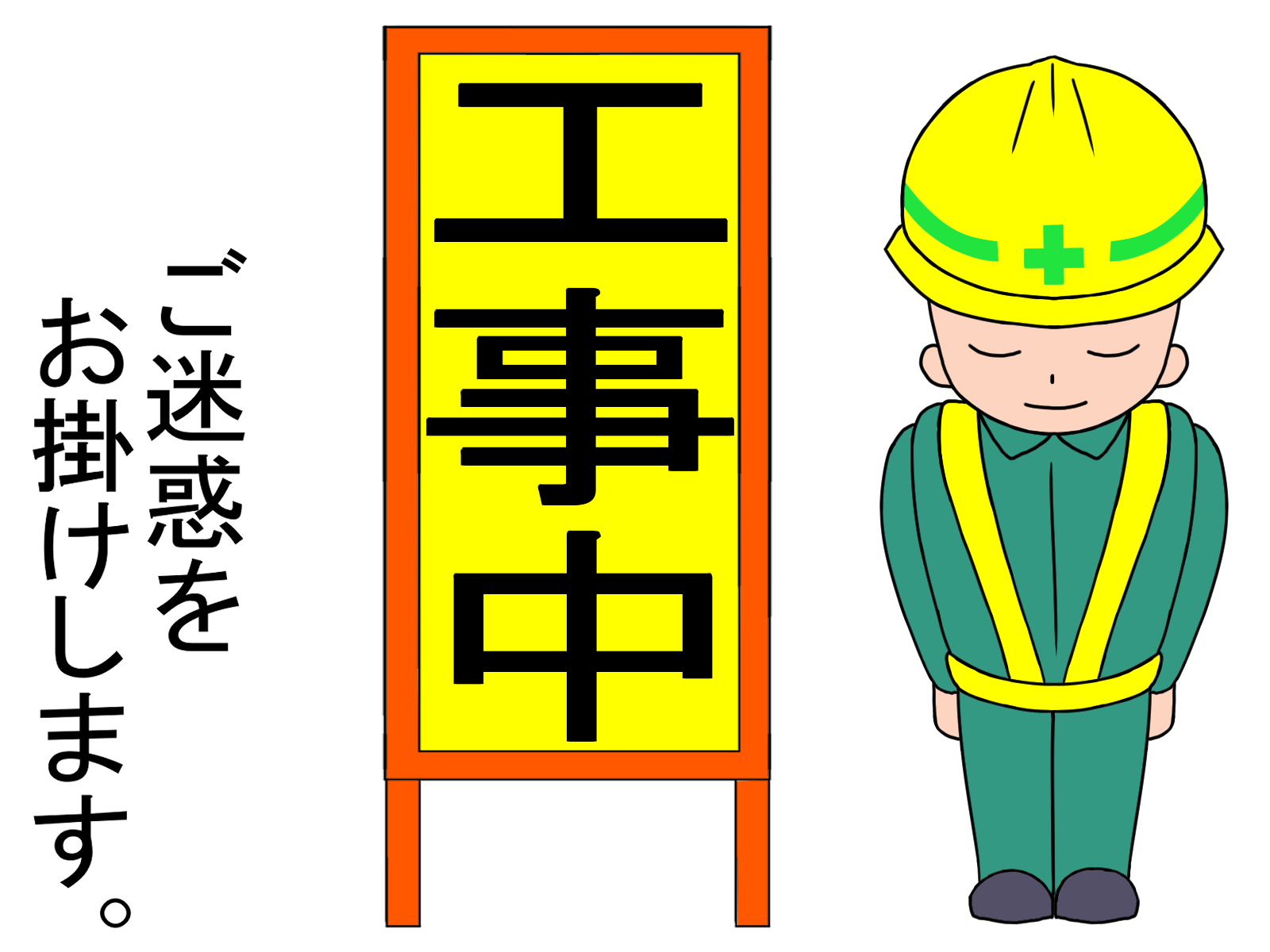本話は、1967年の元旦に放映されたエピソードである。
テレビ界は、時代と景気によってかなり左右されるが、正月、それも元旦ともなれば特別編成番組を放映するのが普通であり、まだまだコンテンツが充実していなかった60年代とはいえ、レギュラー番組が、元旦の日曜日のゴールデンタイムに普通に放映されていたというのは、それだけ『ウルトラマン』(1966年)という番組が、お化け番組であったことの証明でもある。
それは、当事のテレビ界においても快挙であって、そういう意味では本話は、随所で「ウルトラマンとは」を見て取れる作品に仕上がっている。
まずは怪獣娯楽面。
本話ではとにかく、歌舞伎における正月顔見世興行のように、三大怪獣が登場し、画面狭しと大暴れしてみせる、一大娯楽作品としての面が強調されている。
なにはなくとも、当事一番の人気怪獣だったレッドキングの再登場。
今の時代ではレッドキングは、初登場の『怪獣無法地帯』において「ウルトラマンが投げ飛ばしただけで死んだ」という理由で、「実は強い怪獣じゃないのではないか」と揶揄される対象になってしまっているが、それはあくまで現代の視点・価値観で、レッドキングが存在していた当事の怪獣図式を、測っただけに過ぎないということは『怪獣無法地帯』評論で以前に述べたと思う。
少なくとも本放映当事のレッドキングは、並み居るウルトラQ怪獣を蹴散らして君臨した、最強怪獣の称号を欲しいままにしていた怪獣王であり、その最強怪獣王が、改めて新怪獣を二匹率いて、元旦の夜に再登場するとなれば、ウルトラマンに心酔しきっていた子ども達は、チャンネルを合わせない道理がない。
実際、本話は元旦放映にも関わらず、ビデオリサーチ調べで35.7%の数字を弾き出している。
続いて、物語の基本構成を振り返ってみよう。
本話の骨子は、おそらく円谷一氏や金城哲夫氏の意向を取り入れた部分が大きいと思われ、「文明都市を離れた秘境が舞台」「秘境で三匹の怪獣が登場」「怪獣同士の弱肉強食描写」「一匹は無骨タイプ、一匹は飛翔タイプ、そして勝ち残るのはレッドキング」「飛翔タイプはレッドキングに羽根をむしられて敗退」「無骨タイプは科特隊に倒される」「ウルトラマンとの決戦はレッドキング」等々の要素は確実に、『怪獣無法地帯』そのままであり、実質的なプロデュース業務を仕切っていた円谷・金城氏サイドが、元旦放映の一大イベント編に挑むに当たって、飯島敏宏監督に対して、シリーズ屈指の人気娯楽編だった『怪獣無法地帯』の踏襲を要求した要素ではないかと思われる。
いわば本話は『怪獣無法地帯』の、セルフリメイクの側面もあったわけであり、そういった視点で観てみると、金城・円谷・上原のトリオで作られたエピソードを、飯島敏宏・若槻文三コンビで再構成した話とも言える。
飯島監督は、今までの評論で述べたとおり『ウルトラマン』のメイン監督の一人として、様々な角度から世界観や路線の構築に貢献してきた。
コンビを組む脚本家も、旧知の名コンビである藤川桂介氏だけに留まらず、『科特隊出撃せよ』などで山田正弘氏などとも組みつつ、本話ではウルトラシリーズ初登板になる若槻文三氏と組むことで、見事なまでに「SFアンソロジー」と「怪獣バトル」の融合を成功させた。
「宇宙レベルで旅をする彗星が、地球に衝突しようとする危機」というSF設定は、古くは東宝特撮映画の古典名作『妖星ゴラス』(1962年)や、平成以降だとミミ・レダー監督の『ディープ・インパクト』(Deep Impact・1998年)や、マイケル・ベイ監督の『アルマゲドン』(Armageddon・1998年)などでもメジャーな要素であり、ウルトラでも、後に『ウルトラマンA』(1972年)『超獣対怪獣対宇宙人』などで、妖星衝突の危機が描かれるなど、枚挙に暇がないほど普遍的なクライシスなのだが、本話はその状況設定を、あくまで怪獣登場への契機としての背景設定に留めつつ、実は怪獣登場とウルトラマンによるバトルが霞んでしまうほどに、不安感を残す、SFアンソロジー的な余韻を残して終幕を迎えるという、テクニカルな構成で構築されているのである。
「83%」「55860km」「3026年7月」などといった、妙にリアルでありながら、想像が微妙に追いつかない数字の羅列によって描かれる、疑似科学的な悲観的未来観は、これはまさしく、飯島監督の得意とする演出テクニックだろう。
『科特隊宇宙へ』でもみせた、飯島監督の未来科学的語感の操り方は、SF的センスオブワンダーを、日本のテレビでいち早く取り入れたパイオニアでもある。